本記事はプロモーションが含まれています
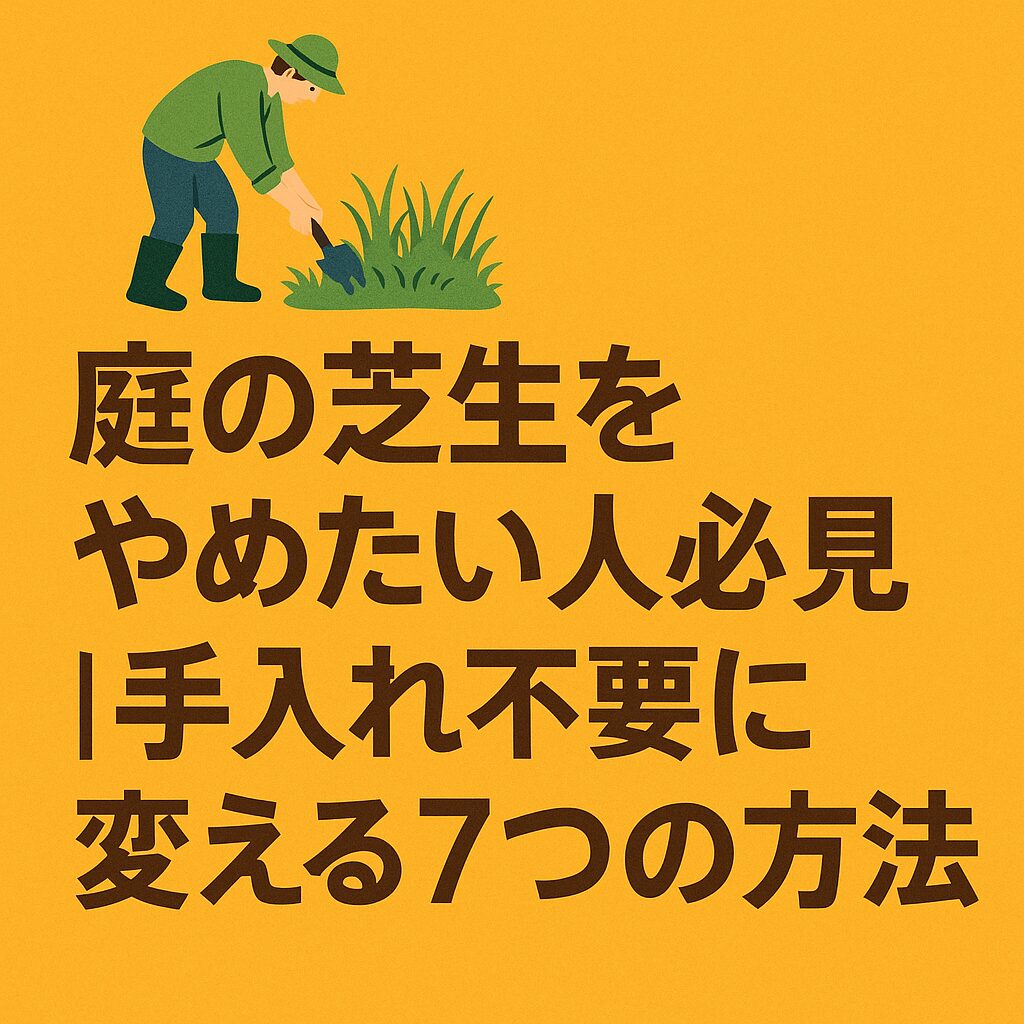
芝生のある庭に憧れて張ってみたものの、
「手入れが大変」
「放置するとすぐに荒れる」
「管理の負担が大きい」
このように感じている方は少なくありません。
この記事にたどり着いた方も、まさに芝生の管理に悩んでいるのではないでしょうか。
芝生は確かに美観を高める魅力的な素材ですが、日々の芝刈り、水やり、雑草取りなどの作業を怠ると、芝が枯れてしまったり、雑草が繁殖したりとトラブルが続出します。
特に「芝を手入れしないとどうなる?」という疑問を持っている方にとっては、実際にどんなリスクがあるのか知っておくことが重要です。
本記事では、「芝生をやめたほうがいい」と判断すべき条件や、「庭の芝生をやめたい」と考えている方向けの具体的な手順、そして砂利やタイルなど芝より手入れが楽な代替素材についても紹介します。
なかには「芝生をやめてタイルを敷く方法」や「砂利の敷き方」によって、庭のメンテナンスが大幅に軽減されるケースもあります。
また、「芝生を植えてから1ヶ月は毎日水やり必要?」といった基本的な疑問から、「芝生は何年くらい持つ?」「芝生は踏んだ方がいい?」「刈った芝の使い道」「やめる費用の目安」など、芝生に関するよくある悩みや誤解についても丁寧に解説します。
すでに雑草だらけの庭になってしまった方でも、「雑草だらけの芝生を復活させる方法」はあるのかどうか、選択肢を知ることで今後の方針が見えてくるはずです。
これからの庭づくりをより快適に、ストレスなく楽しむために、芝生の維持に限界を感じている方へ向けた、実用的かつ現実的な対策をお伝えします。
本記事では、以下のポイントを中心に詳しくご紹介します。
この記事を読むポイント
- 芝生の維持には定期的な水やりや芝刈りなどの手間がかかること
- 芝生を放置すると雑草や病害虫が発生しやすくなること
- 芝生をやめて砂利やタイルなど手入れが少ない素材に変更できること
- 芝生を撤去する際の費用や現実的な処理手順があること
-
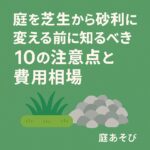
-
庭を芝生から砂利に変える前に知るべき10の注意点と費用相場|庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 庭を芝生から砂利に変えたいと考えている方の中には、 「手入れが大変」「芝生をやめるべきか迷っている」 このように感じている方も多いのではないでしょうか。 この記 ...
続きを見る
庭の芝生をやめたい、もしくは手入れ不要にする方法とは
芝生のある庭は見た目にも美しく、季節の移ろいを肌で感じられる空間として人気があります。
しかし、その美しさを維持するには想像以上に手間がかかるのも事実です。
特に、芝刈り、水やり、施肥、除草といった定期的な作業を怠ると、あっという間に雑草だらけになったり、芝が枯れてしまったりすることもあります。
このような背景から、「手入れ不要で美しい芝生」を実現したいと考える方が年々増えています。
特に、共働き家庭や高齢者世帯、小さなお子さんやペットがいるご家庭では、庭の維持管理にかけられる時間と労力が限られているのが現状ではないでしょうか。
そこで注目したいのが、手間を極力省きつつ、芝生のような緑のある庭を維持する方法です。
芝生の選び方を工夫したり、育て方に一工夫加えたりするだけで、日常の管理負担を大きく軽減することが可能になります。
この記事では、初心者の方にもわかりやすく、手入れが不要に近い芝生の管理方法について具体的にご紹介します。
- 芝生を植えてから1ヶ月は水やり必要?
- 手入れをしない芝生のトラブル事例とは
- 芝生は踏んだ方がいい?
- 芝より手入れ楽な庭材3選【レンガ・砂利・人工芝】
- 芝生を刈らずに済む育て方の工夫とは
芝生を植えてから1ヶ月は水やり必要?
芝生を植え付けてから最初の1ヶ月間は、特に水やりが重要な管理作業になります。
乾燥させてしまうと根がしっかり張らず、その後の生育に大きな差が出てしまうからです。
新たに芝生を張った直後、芝はまだ地面としっかり結びついていない状態です。
この時期は「活着(かっちゃく)」と呼ばれ、芝の根が土に馴染んでいく過程が始まります。
この活着が順調に進まなければ、その後の芝生の見た目や耐久性に悪影響が出てしまいます。
水やりの目安としては、雨が降らない日は毎日、たっぷりと水を与えるのが基本です。
特に晴天や風が強い日などは、乾燥が進みやすいため注意が必要です。
土の表面が乾いているようであれば、朝か夕方にしっかり水を与えるとよいでしょう。
夏場であれば、朝と夕の2回が理想的です。
一方で、過剰に水を与えすぎると常に湿った状態になり、病害虫が発生しやすくなることがあります。
とくに梅雨時期などは、自然降雨が続く場合には水やりを控えるようにしましょう。
芝生の種類によっても耐湿性に差がありますが、一般的な高麗芝やTM9などの日本芝は過湿に弱いため、排水性の良い土壌を保つことも大切です。
このように、植え付け後1ヶ月間は、天候と土の状態を見ながら、こまめに水やりをすることで、芝生の根付きが良くなり、健康な芝に育ちやすくなります。
ポイント
- 活着のために毎日たっぷり水やりが必要
- 晴天・風が強い日は朝夕の2回が理想的
- 過湿になると病害虫が発生しやすいため注意
手入れをしない芝生のトラブル事例とは
芝生を長期間放置してしまうと、見た目だけでなく、機能面でもさまざまなトラブルが発生する可能性があります。
単に「多少伸びても大丈夫」と油断していると、取り返しのつかない状況に陥ることもあるため注意が必要です。
代表的なトラブルとしてまず挙げられるのは、「軸刈り」と呼ばれる現象です。
芝生は通常、葉の部分だけを刈ることで密度を保ちますが、手入れをせずに長期間放置すると、成長点が上に移動してしまいます。
この状態で通常の高さに刈り込むと、根元の茎まで一緒に切ってしまい、芝が弱って枯れてしまうことがあります。
また、手入れを怠ると、雑草が芝の隙間を狙って勢力を広げてきます。芝生が密に生えていれば、雑草の侵入をある程度防げますが、放置された芝は密度が低下するため、雑草にとっては格好の環境となります。
とくに多年草の雑草は根が深く、簡単には除去できないため、早期の対処が求められます。
病害虫の発生も、放置された芝生に多いトラブルの一つです。
湿度の高いまま芝が密に伸びると、風通しが悪くなり、菌や害虫が繁殖しやすい環境になります。
夏場には特に注意が必要で、カビやキノコが発生したり、根を食害するコガネムシの幼虫などが繁殖するリスクもあります。
このように、芝生は「放っておいても自然に育つもの」と考えがちですが、一定の手入れを怠るとさまざまな問題が生じ、最終的には全張替えが必要になることもあります。
無理のない範囲で、最低限のメンテナンスは欠かさないようにしましょう。
ポイント
- 軸刈りで芝が枯れる原因になる
- 雑草が侵入しやすくなる環境に変化する
- 風通しが悪くなり病害虫が発生しやすい
芝生は踏んだ方がいい?
芝生は「なるべく踏まないほうがいい」と思われがちですが、実際には適度に踏むことが芝生の健康維持に役立つケースもあります。
ただし、それが当てはまるのは芝の種類や状態によるため、注意が必要です。
特に日本芝である高麗芝やTM9は、踏まれることに比較的強い品種として知られています。
これらの芝は、運動場や公園などにも使用されることがあるほど耐久性に優れており、適度な踏圧が入ることで芝の茎が締まり、密度が高くなるというメリットがあります。
一方で、芝生の成長点が安定していない植え付け直後や、極端に乾燥しているときなどは踏みつけによりダメージを受けることもあります。
特に、活着前の芝や、雨の直後で地面がぬかるんでいる状態では踏まないように気をつけましょう。
地面がやわらかいと芝の根が動いてしまい、活着の妨げになる可能性があります。
また、西洋芝など一部の寒地型芝生では、踏圧にあまり強くない種類も存在します。
これらは観賞用に適している場合が多く、頻繁に踏まれるとすぐに傷んでしまう傾向があります。
つまり、「芝生は踏んだ方がいいかどうか」は一概には言えません。
芝の品種、育成状態、季節によって適切な管理方法は異なります。
芝生を日常的に使う場面(子どもの遊び場やペットのスペース)であるならば、踏圧に強い種類を選んだうえで、時々エアレーションを行うなどの工夫を取り入れるとよいでしょう。
ポイント
- 高麗芝やTM9は踏むことで密度が高まる
- 活着前や湿った地面は踏むと根が傷む
- 西洋芝などは踏圧に弱い品種もある
芝より手入れ楽な庭材3選【レンガ・砂利・人工芝】
芝生の美しさに憧れはあっても、維持管理の手間や季節ごとの作業負担に悩む方は多いのではないでしょうか。
そんなとき、芝生に代わる「手入れの楽な庭材」を選ぶことで、庭づくりのハードルを大きく下げることができます。
ここでは、特に人気が高い「レンガ」「砂利」「人工芝」の3つに絞って、それぞれの特徴と選び方のポイントを解説します。
レンガ
レンガは装飾性が高く、雑草を防ぎながら庭全体の印象を引き締める効果があります。
施工には多少手間がかかりますが、一度敷いてしまえば基本的にメンテナンスはほぼ不要です。
特に防草シートと組み合わせることで、雑草の侵入を限りなく抑えられます。
カラーバリエーションも豊富で、アンティーク調やナチュラル系など好みに合わせた演出が可能です。
ただし、コストは芝生よりやや高くつく傾向があるため、部分的な使用から始めるとよいでしょう。
砂利
砂利は、もっとも手軽でコストパフォーマンスに優れた素材です。
必要な道具は少なく、DIYでも比較的簡単に施工できます。
排水性に優れているため、水はけの悪い場所にも向いており、防犯対策にもなります。
歩くと音が出るため、不審者の侵入を防ぐ効果も期待できます。
デザイン面ではやや地味な印象もありますが、カラー砂利や和風・洋風のデザインに合わせた工夫でおしゃれに仕上げることも可能です。
人工芝
人工芝は芝の見た目や肌触りを再現しつつ、ほぼ手入れが不要という理想的な素材です。
近年では、耐久性・通気性・リアルな質感を兼ね備えた高品質な人工芝が増えており、一見して本物と見分けがつかない製品も登場しています。
初期費用は高めですが、長期的な管理コストや労力を考えると非常に合理的な選択肢といえます。
ただし、耐火性の面では天然芝に劣るため、バーベキューや花火など火気の使用には注意が必要です。
ポイント
- レンガは防草性とデザイン性が高く、半永久的に使用可能
- 砂利は安価でDIYも簡単、防犯にも有効
- 人工芝はリアルな見た目で管理不要だが初期費用が高め
芝生を刈らずに済む育て方の工夫とは
芝生を維持する上で最も手間がかかるのが芝刈りです。
特に夏場は生育が旺盛で、頻繁な芝刈りが必要になるため、これが原因で芝生を手放す方も少なくありません。
そこで注目されているのが、「芝刈り不要、または最小限に抑えるための育て方」の工夫です。
完全に刈らずに済ますのは難しいものの、工夫次第で管理の負担は大きく軽減できます。
まず第一に、芝の品種選びが重要です。
中でも「高麗芝」やその改良品種である「TM9(ティーエムナイン)」は、生育が緩やかで芝刈り頻度を抑えられることで人気があります。
一般的な高麗芝が月2〜3回の芝刈りを必要とするのに対し、TM9なら月1〜2回程度で済み、作業負担を大きく削減できます。
このように、初期段階で適切な芝の種類を選ぶことが、後のメンテナンスを楽にするカギとなります。
次に、芝刈り機の選定と収納場所の工夫も見落とせません。
面倒だからといって芝刈り機を倉庫の奥に片づけてしまうと、出すだけで億劫になりがちです。
すぐに手に取れる位置に収納しておくだけでも、思い立った時にスムーズに作業できます。
また、集草機能付きの芝刈り機を使用することで、刈った芝の処理を省略できる点も大きな利点です。
さらに、庭のレイアウト設計も重要な工夫ポイントです。
例えば、キワ(芝生と壁や境界の接する部分)にはあらかじめ芝を張らず、レンガやタイルで縁取りしておくことで、「キワ刈り」の手間を減らせます。
この部分は通常の芝刈り機では刈りにくく、手作業での対応が必要になるため、事前に施工段階で対策しておくと管理がずっと楽になります。
これらの方法を組み合わせることで、芝刈りを“面倒な作業”から“日常のちょっとしたルーティン”に変えることができます。
育て方に工夫を凝らすことは、長期的に見ればコストと労力の節約に直結し、ストレスの少ない芝生活を実現する手段となるのです。
ポイント
- TM9など成長が遅い芝を選ぶと芝刈り頻度を減らせる
- 境界に芝を張らずレンガなどを使うと手入れが楽になる
- 芝刈り機の収納場所を工夫することで作業の心理的負担も軽減
-

-
庭を芝生以外にしたい!プロがすすめる代替素材ベスト5 | 庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 芝生は見た目に美しい一方で、芝刈りや水やり、雑草取りなど、日々のメンテナンスに手間がかかる点が課題です。 「庭の芝生をやめたい…」と感じている方にとって、芝生の ...
続きを見る
庭の芝生をやめたい、もしくは手入れ不要に変える具体策
芝生を手入れする時間や体力がない、もしくは年々その作業が負担に感じるようになってきた…
そうした理由から「芝生をやめたい」と考える方は少なくありません。
実際、長期的な目線で見れば、芝生の維持管理には一定の労力とコストがかかります。
特に夏場の頻繁な芝刈りや水やりに疲弊してしまうケースも多く、芝生がもたらす癒しよりも負担感のほうが大きくなることもあります。
一方で、芝生を完全に撤去したり、他の素材に置き換えたりするには、それなりの手順と費用が伴います。
また、「芝生を一部だけ残したい」「使い勝手のよい庭に変えたい」といったケースもあるため、単純な撤去だけでなく、目的に合った工夫が求められます。
この章では、芝生を手放したいと考える方のために、どのような条件で芝生をやめたほうがいいのか、実際に撤去する際の手順や注意点、そして代わりに取り入れやすい庭材について解説していきます。
これから庭づくりを見直したいと考えている方にとって、具体的な選択肢を整理する手がかりになるはずです。
- 芝生をやめたほうがいいと判断される条件とは
- 芝生をやめたい人のための現実的な処理手順
- 芝生をやめてタイルを敷くメリットと注意点
- 砂利敷きの庭は本当に手入れが楽になるのか?
- 芝生をやめる費用の目安とコストを抑える方法
- 刈った芝の処分と再利用アイデアまとめ
芝生をやめたほうがいいと判断される条件とは
芝生は見た目の美しさや触り心地が魅力ですが、すべての家庭にとって最適な選択とは限りません。
実際、管理の負担や環境の相性などから「芝生をやめたほうがいい」と判断されるケースは少なくありません。
判断に迷っている方は、以下のような条件に当てはまるかどうかを一度見直してみましょう。
まず、定期的な芝刈りや水やり、肥料などの手入れが難しい環境では、芝生の維持が負担になりやすいです。
特に共働き世帯や高齢者の方にとって、月に数回の芝刈りや夏場の水やりは大きな手間となります。
また、芝生は「放置=劣化」に直結するため、管理の余裕がない状況では、美観が損なわれるだけでなく、雑草や病害虫の温床になるリスクもあります。
次に、日当たりや風通しが悪い立地も、芝生にとっては厳しい環境です。
芝生は光合成によって健康を保つため、半日陰や北向きの庭では生育不良を起こしやすく、地面が剥げる、苔が繁殖するなどの問題が出やすくなります。
こうした土地に無理に芝を植えても、手入れに比例して成果が出にくいため、コストと労力が無駄になってしまうことも少なくありません。
また、小さなお子さんやペットが頻繁に走り回るような庭では、芝が擦り切れやすくなります。
ある程度の踏圧には耐える品種もありますが、過度な利用によって禿げた部分が目立つと、かえって手入れの手間が増える結果にもつながります。
- 「ライフスタイル」
- 「庭の環境」
- 「利用頻度」
上記3つの視点から見て、芝生との相性が悪いと感じた場合は、別の庭材への切り替えを検討することも合理的な選択と言えるでしょう。
ポイント
- 日当たりや風通しが悪い庭では芝の維持が難しい
- 忙しい生活で定期的な手入れが難しい人には不向き
- 子どもやペットの頻繁な利用で芝が禿げやすい庭も注意
芝生をやめたい人のための現実的な処理手順
芝生をやめると決めたら、まずはどのように撤去し、次の地面処理へつなげていくかを考える必要があります。
芝生の撤去は手間がかかる作業ですが、順序を把握しておくことで、無駄なく効率的に進めることができます。
第一段階は、芝生の除去方法の選定です。
主に3つの方法があり、それぞれ特徴があります。
1「掘り出し」
スコップで芝の根ごと剥がしていく最も確実な方法です。ただし、広範囲だと労力が大きく、数日かかることもあります。
2「除草剤の使用」
非選択性の除草剤を散布し、数日〜数週間かけて芝を枯らす方法で、比較的手軽に実行できます。
ただし、除草剤の種類によっては、次の植栽までの期間を空ける必要があります。
3「日光遮断」
新聞紙や黒いビニールシートなどで芝生を覆い、光合成を阻止して枯らす方法です。
薬剤を使いたくない人に適していますが、完全に枯れるまでに1〜2か月かかることがあります。
次に行うのが芝の処分と整地作業です。
掘り出した芝には根や土がついているため、自治体のルールに従い「植物系ごみ」と「土砂類」に分けて廃棄する必要があります。
この点は地域によって異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
除草剤や日光遮断を使った場合でも、枯れた芝をそのまま放置するのは避け、土ごと軽く掘り返して整地しておきましょう。
最後に、次に敷く素材(タイル・砂利・人工芝など)に合わせた下地づくりを行います。
例えば人工芝の場合、防草シートの敷設と転圧、排水性を考慮した砂の整地が求められます。
DIYでできる範囲もありますが、不安な場合は部分的に業者へ依頼するのも手です。
このように、芝生をやめる作業は数段階に分かれますが、計画的に進めれば無理なく実行できます。慌てず段取りを組むことが成功のポイントです。
ポイント
- 掘り起こし・除草剤・日光遮断など方法に応じた準備が必要
- 地域によって処分方法が異なるため事前確認が大切
- 次に敷く素材に応じて整地や防草シートの準備も忘れずに
芝生をやめてタイルを敷くメリットと注意点
芝生の代わりにタイルを敷くという選択は、庭の手入れ負担を大きく軽減しつつ、見た目にも整った印象を与える方法の一つです。
日々の管理を最小限に抑えたい方や、屋外空間を実用的に使いたいと考えている人には非常に相性の良い選択肢といえるでしょう。
メリットとしてまず挙げられるのは、定期的な手入れがほとんど不要になる点です。
芝生と違い、タイルは成長も変化もありません。
そのため芝刈りや水やり、施肥といったメンテナンス作業は不要になります。
防草シートを下に敷いておけば、雑草の発生も最小限に抑えられるため、草取りに追われることもありません。
また、屋外のテーブルやチェアを置いてくつろぐスペースとしても活用しやすくなります。
見た目に関しても、タイルには様々な色・形・素材があるため、住宅の外観や好みに合わせてデザイン性の高い空間を演出できます。
とくにアンティーク調やモダン系のタイルを使えば、雑誌に出てくるようなおしゃれな庭づくりが可能です。
ただし、いくつか注意点もあります。
特に気をつけたいのは排水性と熱の蓄積です。
タイルは水を吸収しないため、平坦すぎると雨水が溜まりやすくなります。
施工時にわずかな傾斜をつける、または側溝を設けるなどして排水の工夫が必要です。
また、夏場は日差しを反射して非常に熱くなることがあり、小さなお子様やペットがいる家庭では注意が必要です。
さらに、施工には一定の費用と手間がかかります。
DIYも可能ではあるものの、下地づくりや水平調整に失敗すると見た目や耐久性に影響が出るため、不安な場合は専門業者に依頼する方が安心です。
このように、芝生からタイルへと変更することで維持管理は格段に楽になりますが、施工や設計段階での配慮が求められます。
しっかりと計画を立てた上で進めることが、後悔しない庭づくりへの第一歩になります。
ポイント
- 手入れ不要でくつろぎスペースにも活用できる
- 水はけや照り返し、施工精度に注意が必要
- DIYも可能だが、失敗しやすい部分は業者に依頼を検討
-

-
庭を芝生からタイルで快適!初心者向けの手順と注意点7つ | 庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 「庭の芝生をタイルに変えたい…」 上記のような悩みを抱える人の多くは、芝生の管理に疲れ、もっと手入れの少ない庭づくりを検討しているのではないでしょうか。見た目の ...
続きを見る
砂利敷きの庭は本当に手入れが楽になるのか?
芝生に代わる庭の管理法として、砂利敷きは「手入れが楽になる」として広く知られています。しかし、本当にすべての場面で楽になるのかといえば、必ずしもそうとは限りません。メリットだけでなく、実際に発生する作業や注意点も踏まえた上で選択することが大切です。
砂利の大きな特長は、雑草が生えにくくなることです。地面に直接砂利を敷くだけでは効果が薄くなりますが、防草シートと組み合わせることで雑草の発生を大幅に抑えることができます。これにより、定期的な草取りや芝刈りといった作業から解放され、年間を通して管理の手間が減るという点は大きな魅力です。
また、砂利は水はけが良く、雨の日でもぬかるみにくいため、靴が汚れにくく快適に庭を歩けるというメリットもあります。加えて、歩くたびに音が出ることから、防犯対策にもつながるという副次的な効果もあります。
一方で、注意すべき点もあります。まず、砂利の隙間から雑草が出ることは完全には防げないということです。特に防草シートが劣化してくると、風で飛ばされた種子が根付くことがあります。また、落ち葉が多くなる季節では、砂利の上に積もった葉を取り除くのが意外と手間に感じることもあります。ブロワーなどの道具があると効率的ですが、手作業だと時間がかかる場面も出てきます。
加えて、砂利は一度敷いてしまうと撤去が大変です。再び芝生や植栽を検討したくなったときに、地面を戻すのが面倒になるケースもあります。見た目についても、デザイン次第では無機質な印象になりやすいため、ナチュラル感を出したい方は色や素材の選定に工夫が必要です。
このように、砂利敷きは芝生に比べて圧倒的に手入れが楽になりますが、全くメンテナンス不要になるわけではありません。庭の用途や周辺環境を踏まえながら、部分使いするなどして、最適な形に調整していくことが理想的です。
ポイント
- 雑草防止・排水性・防犯効果に優れる
- 防草シートが劣化すると雑草が発生しやすくなる
- 落ち葉の掃除や将来の撤去がやや面倒
-
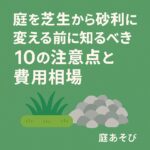
-
庭を芝生から砂利に変える前に知るべき10の注意点と費用相場|庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 庭を芝生から砂利に変えたいと考えている方の中には、 「手入れが大変」「芝生をやめるべきか迷っている」 このように感じている方も多いのではないでしょうか。 この記 ...
続きを見る
芝生をやめる費用の目安とコストを抑える方法
芝生の撤去を考えたとき、気になるのはやはりその費用です。
「芝生をやめて手入れを楽にしたい」と思っていても、どのくらいの予算が必要になるのか見当がつかない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、芝生をやめる際の費用感と、費用を抑えるための現実的な工夫を紹介します。
まず、業者に依頼する場合の費用相場ですが、1㎡あたり2,000〜5,000円程度が目安となります。
この中には、芝生の剥がし作業、廃棄処理、簡易な整地作業が含まれることが多いです。
広い面積の場合はこの単価に比例して全体コストが大きくなるため、50㎡であれば10万円以上になることも珍しくありません。
一方で、DIYで対応する場合は、費用を大きく抑えることが可能です。
たとえば、スコップやレーキ、防草シートなど基本的な道具類にかかる初期費用は1万円前後に収まることが多く、処分費も自治体のルールに従えば無料または低額で済むケースがあります。
ただし、手間と時間は相応にかかるため、体力や作業スペースの余裕が必要です。
費用を抑えるもう一つの方法としては、部分的に芝生を残し、メンテナンスしやすい形に整えるという選択肢があります。
庭の中央や人がよく通る部分だけをタイルや砂利に変え、目立たない場所はそのままにしておくことで、作業負担とコストのバランスをとることができます。
また、芝生撤去後の地面に何を敷くかもコストに影響します。
人工芝やタイルなどは初期費用がかかる反面、長期的にはメンテナンス費用を抑えられる利点があります。
逆に、砂利やウッドチップは比較的安価に始められますが、数年ごとに補充が必要になることもあります。
このように、芝生をやめる際には単に「剥がすだけ」でなく、「その後どうするか」も含めて計画することが大切です。
自分の暮らし方に合った範囲で進めることで、無理なく、費用を抑えながら理想の庭づくりを目指すことができます。
ポイント
- 業者依頼では1㎡あたり2,000〜5,000円が目安
- DIYなら費用は抑えられるが体力と時間が必要
- 一部だけ残す方法や安価な素材を使うことで節約可能
刈った芝の処分と再利用アイデアまとめ
芝生を管理していると、必ず発生するのが「刈った芝(刈草)」の処分問題です。
量が多くなるとゴミ袋がすぐにいっぱいになってしまい、処理に困るという声も少なくありません。
ここでは、刈った芝を適切に処分する方法と、意外と知られていない再利用のアイデアを紹介します。
まず、処分方法として最も一般的なのは、自治体のルールに従って「可燃ごみ」や「草木類」として出す方法です。
ただし、地域によっては量が多すぎると収集対象外になる場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、土が付いていたり、湿っていると臭いが発生しやすいため、できるだけ乾燥させてから出すのが望ましいです。
一方で、刈った芝は「再利用資源」として活用できる場面もあります。
最も手軽なのは、マルチング材としての利用です。
花壇や野菜畑の根元に薄く敷いておくことで、土の乾燥を防ぎ、雑草の発生も抑える効果が期待できます。
ただし、厚く敷きすぎるとカビや虫が発生する原因になるため、通気性を確保しながら使用することが大切です。
また、家庭用の堆肥(コンポスト)材料としても利用可能です。
芝は窒素分を多く含んでおり、落ち葉などと組み合わせて積層しておけば、数か月後には自家製のたい肥としてガーデニングに使えるようになります。
この場合も、芝だけでなく枯葉や米ぬかなどを混ぜることで、バランスの良い分解が進みます。
もし庭に余裕があるなら、乾燥させて草木灰として利用する方法もあります。
ただし、芝生を燃やす行為には地域によって規制がありますので、必ず自治体のルールを確認したうえで行うようにしましょう。
このように、刈った芝はただのゴミではなく、うまく使えば庭づくりに役立つ資源になります。
手入れの中で発生する副産物を賢く活用することで、より循環的でエコなガーデンライフが実現できるでしょう。
ポイント
- 乾燥させて可燃ごみや草木類として処分が基本
- 花壇へのマルチングや家庭用堆肥に活用できる
- 自治体ルールを守れば灰としても使える場合がある
-

-
庭にソテツをおしゃれに植える!映える配置と育て方の極意32選
本記事はプロモーションが含まれています 庭にソテツをおしゃれに!配置・育て方・剪定の基本まとめと32のテクニック 南国風の雰囲気を手軽に演出できる植物としては人気のソテツは、その独特な存在感から「庭に ...
続きを見る
【まとめ】庭の芝生をやめたい、もしくは手入れ不要にする方法

芝生のある庭は美しく魅力的ですが、放っておくと手間やコストがかかるのも事実です。
芝生管理に悩む方や、もっと手入れの少ない庭づくりを目指す方に向けて、これまで紹介してきた知識を総括します。
以下のポイントを意識すれば、芝生のある庭でも手間を抑えた快適な空間づくりが可能になります。
この記事のまとめ
- 芝生を植えた直後の1ヶ月は毎日の水やりが大切
- 活着期間は土の湿り具合を見ながら丁寧に管理する
- 芝生を放置すると病害虫や雑草の被害が増える
- 定期的な芝刈りをしないと芝が枯れるリスクが高まる
- 踏圧に強い品種は適度な踏みつけで密度が高くなる
- TM9などの省管理型芝生は手間を大きく減らせる
- 人工芝や砂利は芝よりメンテナンスが格段に楽
- タイル敷きにすれば雑草対策にもつながる
- 雨の日のために排水設計は慎重に行う必要がある
- 庭の一部だけ芝をやめる部分施工も効果的
- DIYなら芝生撤去費用を大幅に削減できる
- 刈った芝はマルチング材や堆肥として再活用できる
- 防草シートの併用で砂利敷きの維持が容易になる
- 陽当たりや家族構成によっては芝生をやめた方が合理的
- 継続できる管理方法を選ぶことが庭の長寿命化につながる
このように、庭の芝生を手入れ不要にするためには、日々の作業を見直すだけでなく、そもそもの素材選びや設計段階での工夫が欠かせません。
ご自身のライフスタイルに合った選択をすることで、無理のない快適な庭づくりを実現を目指してくださいね!
◎庭の芝生を手入れ不要に変える7つの方法
- 人工芝への張り替え
- 庭を砂利敷きに変更する
- レンガやタイルで舗装する
- 芝刈りの負担を減らす芝品種を選ぶ
- 庭の一部のみ芝生を残す部分活用法
- 芝を撤去して防草シートを活用する
- 刈った芝の再利用で手入れ効率アップ
芝生の手入れについて知りたい際にあるよくある質問(FAQ)
-
今の芝生、正直ほぼ放置なんですが…このままにしておくとどうなりますか?
-
放置された芝生は、まず雑草だらけになりやすく、密度が落ちてスカスカになります。
さらに、伸びすぎた状態で一気に短く刈ると「軸刈り」になり、茎ごと傷つけて広範囲が茶色く枯れることも。風通しも悪くなるので、カビ・キノコ・害虫(コガネムシ幼虫など)が増えやすい環境になってしまいます。
「見た目が悪い」「虫が増える」「最終的に張り替えレベルの大工事」につながるので、維持が無理そうなら“やめる・別素材に変える”という選択も十分アリです。
-
芝生をやめるとしたら、砂利・タイル・人工芝って結局どれが一番ラクですか?
-
“ラクさ”の種類が少し違います。
- 砂利:
初期費用が安くDIYしやすい/雑草対策&防犯(歩く音)◎/ただし落ち葉掃除と、年数が経つと雑草ゼロにはならない。 - タイル:
芝刈りも草取りもほぼ不要/テラス的にイス・テーブルも置きやすい/ただし施工費が高めで、水はけと夏の照り返しには要注意。 - 人工芝:
見た目はほぼ芝、でも芝刈り・水やり不要/子どもの遊び場にも人気/ただし初期費用が高め、火気NG・経年劣化でいつか交換が必要。
「見た目も重視で長く使いたい」なら人工芝やタイル、「コストを抑えて手入れを減らしたい」なら砂利+防草シートが選ばれやすいです。
- 砂利:
-
業者に頼むと高そう…芝生の撤去って自分でやっても大丈夫?
-
DIYでも十分可能ですが、「体力勝負&時間がかかる」作業だと思っておいたほうが安心です。
- DIYの基本ステップ
- スコップで芝を“皮”のようにめくりながら剥がす
- 根や土を振るい落としつつ、自治体ルールに従ってゴミに出す
- 地面をならし、防草シートや砂・砂利など次の素材に応じて整地
道具代+処分費で、概ね1万円前後〜で収まることも多いですが、面積が広い/腰や膝に不安がある場合は、「端のほうだけDIYで、メインは業者にお任せ」といった“併用パターン”も現実的です。
- DIYの基本ステップ
-
完全に芝をやめるのは少し寂しい…一部だけ残すってありですか?
-
もちろんアリですし、むしろ「部分的に芝を残す」のはかなり合理的な選択です。
例えば
- 家の出入りが多い動線 → 砂利 or タイルで土汚れ・雑草対策
- 子どもの遊ぶゾーン or ペットのくつろぎスペース → 芝 or 人工芝
- 建物際やキワ → 芝を張らずレンガ・タイルで縁取りして「キワ刈り」をなくす
こうすると、「芝生は楽しみつつ、手入れが重いところだけ別素材に変える」というバランスが取れます。全部やめるか・全部続けるかの二択ではなく、“使い方に合わせて残す部分を決める”のがおすすめです。
-
これから芝生を張り替えたり、続けるなら最低限どこだけ気をつければいいですか?
-
「フルメンテナンス」は無理でも、以下を押さえるだけでかなりマシになります。
- 張りたて1ヶ月の水やり:
雨がない日は毎日たっぷり。夏は朝夕2回が理想。 - 伸びすぎる前に刈る:
軸刈り回避のため、「ちょっと伸びたかな?」くらいでこまめに短時間で済ませる。 - 品種選び:
TM9など成長の遅い省管理型を選ぶと、芝刈り回数をぐっと減らせる。 - レイアウトの工夫:
キワは最初から芝を張らずレンガ等で処理しておくと、将来の手間が激減。 - 刈った芝の扱い:
乾かしてゴミに出す or 花壇のマルチング・堆肥材として再利用すると処分もラク。
「完璧を目指さず、続けられるラインで工夫する」と、芝を続けるにしても、やめるにしてもストレスがかなり減ります。
- 張りたて1ヶ月の水やり:


