本記事はプロモーションが含まれています
ソテツが枯れる原因とは?葉を全部切るのは危険?初心者が避けたい7つのミス
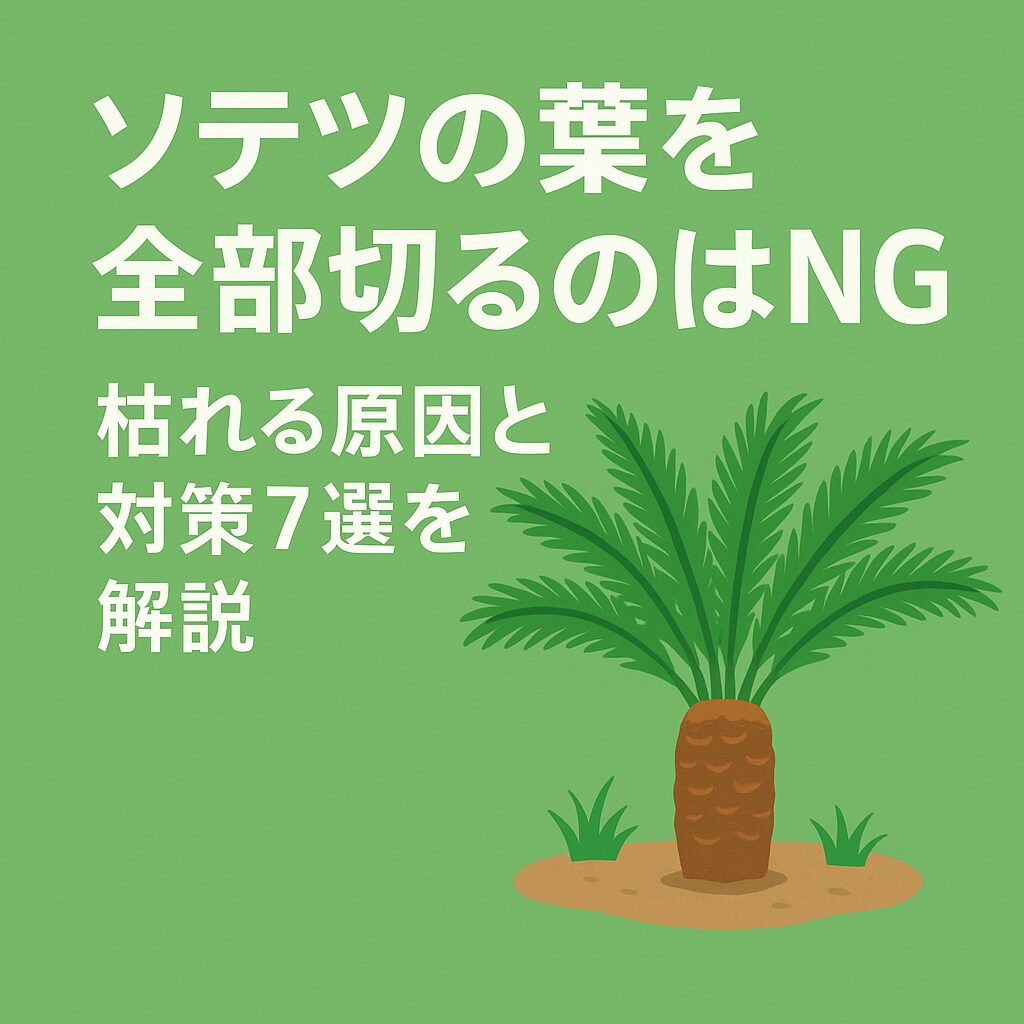
ソテツが枯れてきたと感じたとき、
「葉を全部切ってしまっても大丈夫なのか」
「どうすれば復活できるのか」
そんな悩みを持つ方必見。
特に冬に枯れるような症状が出たり、新芽が出ないまま時間が経過していると、不安が大きくなります。
こうしたとき、焦って剪定した結果、かえってソテツが枯れる原因をつくってしまうこともあります。
ソテツが弱る背景には、さまざまな要因が関係しています。
たとえば、水のやりすぎによる根腐れの症状や、長年の植え替え不足による成長の停止、屋外での育て方による寒さのダメージなど、複数の問題が絡み合っていることが多いです。
中には、胴切りや丸坊主にする時期を誤ったことで再生が難しくなるケースもあります。
この記事では、ソテツが枯れる原因をひとつずつ紐解きながら、葉を全部切る前に知っておきたい判断基準や復活の可能性について詳しく解説していきます。
屋外で育てている方、新芽が出ないことに悩んでいる方、そして今まさに対処を迷っている方にとって、参考になる内容をお届けします。
この記事を読むポイント
- ソテツが枯れる主な原因とその見極め方が分かる
- 葉を全部切る判断が適切かどうかの基準が分かる
- 冬や過湿によるダメージへの対処方法が分かる
- 根腐れや根詰まりなど根の異常の確認方法が知れる
目次
ソテツが枯れる原因|葉を全部切るのは正解?

ソテツの葉が黄色くなったり、しおれたりしているのを見て、「もう枯れてしまったのでは?」と心配になる方は少なくありません。
そうした場合、見た目をリセットするように葉をすべて切ってしまいたくなるかもしれませんが、その判断は慎重に行う必要があります。
なぜなら、葉が変色したからといって即座に「完全に枯れた」とは限らず、適切に管理すれば回復する可能性があるためです。
まず確認すべきは、枯れたように見える原因が何かという点です。
水のやりすぎや不足、寒さによるダメージ、根詰まり、害虫の発生など、さまざまな要因が複雑に絡み合っている場合があります。
こうした原因を一つひとつ丁寧に確認することで、誤った判断を避けることができるのです。
葉は光合成を行い、ソテツの生命活動に欠かせない役割を果たしています。
そのため、すべての葉を一度に切ってしまうと、植物に大きな負担がかかってしまいます。
特に、新芽がまだ出ていない状態で全ての葉を取り除いてしまうと、エネルギー不足により回復が困難になるリスクも高まります。
葉を全部切るという対処法には一定の効果がある場面もありますが、それはあくまで「葉の多くが明らかに枯れていて再生の見込みが薄い」と判断できる場合に限られます。
まずは枯れの原因を見極め、必要であれば部分的な剪定から試みるとよいでしょう。
このように、「葉を全部切る」という選択は最後の手段であり、必ずしも最初に行うべき処置ではありません。
むしろ、ソテツの状態を冷静に観察し、根本的な問題の解決を目指すことが、健康な成長を取り戻す近道となるのです。
- 枯れる原因を見極めて対処する
- 根腐れの症状を見分けるポイント
- 剪定でソテツが枯れることはある?
- 新芽が出ない場合の対処法とは
枯れる原因を見極めて対処する
ソテツが枯れ始めていると感じた場合、まず必要なのは「なぜ枯れているのか」を正しく判断することです。
ただ葉が黄色くなっているからといって、必ずしも完全に枯れているとは限りません。
誤った処置を避けるためにも、原因を一つひとつ見極めていく姿勢が重要です。
まず注目すべきなのは、水のやりすぎや不足です。
特に鉢植えの場合は、水を頻繁に与えすぎると根腐れを起こしやすくなります。
一方、地植えのソテツでは雨水で十分に育つケースが多く、水を追加で与える必要はほとんどありません。
葉がしおれてきたり、色がまだらに変化している場合、水分管理を見直してみてください。
次に考えられるのが寒さによるダメージです。
ソテツはもともと温暖な地域を原産とする植物のため、5度以下の環境にさらされると弱りやすくなります。
特に冬場に屋外で育てている場合、寒風や霜が原因でダメージを受けている可能性があります。
寒さ対策としては、室内へ移動させるか、幹を藁などで保温する方法が有効です。
また、根詰まりも見逃してはならない要因の一つです。
長年同じ鉢で育てていると、根が密集して水分や養分をうまく吸収できなくなります。
この場合は、根の状態をチェックして適切なタイミングで植え替えを行う必要があります。
さらに、害虫の発生もソテツの健康に大きな影響を与えることがあります。
カイガラムシやソテツシジミの幼虫などが葉や新芽を食害し、成長を妨げてしまうことがあるため、葉の裏や茎の周辺を定期的に観察しましょう。
以上のように、ソテツが枯れ始めている場合は単一の原因ではなく、複数の要因が絡んでいることもあります。
まずは「葉・幹・根」の3つの状態をしっかり観察し、症状ごとに適切な対処を行うことが、ソテツを元気に育てるポイントです。
ポイント
- 葉が黄色くなっていても完全に枯れているとは限らない
- 水のやりすぎや不足が枯れの大きな要因になる
- 寒さや霜の影響でダメージを受けることがある
- 根詰まりや害虫被害も枯れの原因として要注意
根腐れの症状を見分けるポイント
ソテツの元気がないときに真っ先に疑われるのが「根腐れ」です。
これは、土壌内の過湿状態が続いた結果、根が酸欠を起こし、腐敗してしまう現象です。
見た目には葉のしおれや変色といった症状が現れますが、外観だけでは他の原因と区別がつきにくいため、判断にはいくつかのポイントを確認する必要があります。
まず確認すべきなのは葉の様子です。
根腐れを起こしているソテツでは、葉が一斉にしおれたり、黄色や茶色に変色する傾向があります。
特に中心から外に向かって葉が弱っていく場合、水分をうまく吸い上げられていないサインである可能性が高いです。
次に、根の状態を直接チェックすることも重要です。
ソテツを鉢から抜いて根を観察すると、正常な根は白くてハリがあるのに対し、根腐れを起こした根は黒っぽくなり、触ると柔らかく崩れやすい特徴があります。
臭いを確認すると、腐敗臭がすることもあります。
これらの状態が確認できた場合は、根腐れの進行がかなり進んでいると考えてよいでしょう。
また、土の状態もヒントになります。
土が常に湿っていたり、排水性が悪いまま放置されていると、根に酸素が供給されず腐りやすくなります。
鉢底から水が出にくかったり、受け皿に水がたまっている場合は要注意です。
対策としては、腐った根をハサミで切り取り、残った健康な根だけを残して植え直す方法が一般的です。
その際、土も新しいものに入れ替え、通気性・排水性の良い用土を使うようにしましょう。
さらに、植え直したあとは数日間乾燥させてから水やりを再開することで、再発のリスクを抑えられます。
このように、ソテツの根腐れは外見だけでは分かりにくいこともありますが、細かく観察していくことで比較的早い段階で気づくことができます。
日ごろから土と根の状態を意識して管理することが、健全な育成につながるでしょう。
ポイント
- 葉が一斉にしおれる・変色するなどの兆候が見られる
- 腐った根は黒く柔らかく、悪臭を放つことがある
- 土が常に湿っている、排水性が悪いと根腐れしやすい
- 腐敗根を切除し、通気性・排水性の高い土で植え替える
剪定でソテツが枯れることはある?
ソテツは比較的強健な植物として知られていますが、不適切な剪定によって枯れてしまうことがあります。
見た目を整えたり、古くなった葉を取り除いたりする目的で剪定を行う場合でも、方法を誤ると植物全体の健康に大きなダメージを与えるため注意が必要です。
まず押さえておきたいのは、すべての葉を一度に切り落とすのは避けるべきということです。
葉は光合成によってソテツのエネルギー源となる重要な役割を果たしています。
仮にすべての葉を剪定してしまうと、光合成ができずに新しい芽や根を成長させるためのエネルギーが確保できなくなってしまいます。
このような状態が続くと、ソテツは弱っていき、やがて枯れてしまうこともあるのです。
また、時期にも注意が必要です。
ソテツの剪定は成長が活発な春から初夏にかけて行うのが望ましいとされています。
このタイミングであれば新芽の発育が見込めるため、多少の葉を落としても回復しやすい傾向があります。
一方、冬場の休眠期に剪定を行うと、寒さと回復力の低下が重なり、植物に過剰なストレスを与えてしまいます。
剪定時の切り口にも配慮が必要です。
鋭利な剪定バサミを使用してスパッと切ることが大切で、雑に切ったり裂けたりすると、細菌やカビなどの病原体が侵入しやすくなります。
可能であれば切り口に殺菌剤や癒合剤を塗布しておくと安心です。
つまり、剪定自体は間違いではありませんが、「すべての葉を切る」「時期が悪い」「切り方が乱暴」といった要素が重なると、枯れる原因になってしまいます。
健康なソテツを保つためには、剪定の目的・方法・時期の3点を常に意識して行うことが重要です。
ポイント
- 葉を全部切り落とすと光合成ができず弱る原因になる
- 剪定は春から初夏の成長期に行うのが理想
- 冬の剪定はダメージ回復が遅れ、リスクが高まる
- 雑な切り口は病気のもとになるため清潔な道具を使う
新芽が出ない場合の対処法とは
ソテツは新芽が出ることで成長を続ける植物ですが、なかなか新芽が出てこない場合には、いくつかの原因が考えられます。
焦って無理な処置をする前に、まず環境や育て方を見直すことが肝心です。
一般的に、新芽の発生が見られるのは春から夏の暖かい季節です。
そのため、冬の間に新芽が出ないのは自然なことであり、休眠期として静かに過ごしているだけの場合もあります。
ただし、春が過ぎても動きがない場合には、何らかの環境要因が影響している可能性があります。
まずチェックすべきは、置き場所の日当たりです。
ソテツは直射日光を好む植物であり、光が不足すると新芽の発生が鈍る傾向があります。
室内や日陰に長期間置いている場合は、日照時間が十分かどうかを確認し、明るい場所へ移動させてみてください。
次に、水やりと肥料のバランスも影響します。
水を与えすぎると根が傷み、逆に少なすぎると水分不足になります。
また、成長期に十分な栄養が供給されていないと、新しい芽を出す力が不足してしまうこともあります。
緩効性肥料を使って、土壌の栄養状態を整えると改善が見込める場合があります。
さらに注意したいのが根詰まりの可能性です。
長年同じ鉢に植えられているソテツは、根がいっぱいになって新しい成長を妨げていることがあります。
植え替えの目安としては、2~3年に一度の頻度で土を新しくし、根をほぐしてあげるとよいでしょう。
これらの対処をしても改善が見られない場合、植物自体が休眠しているか、深刻なダメージを受けている可能性があります。
その場合は、葉や幹の様子をよく観察し、変色や柔らかさがないか確認してみましょう。
いずれにしても、新芽が出ないと感じたときは、焦らずに環境や管理方法を一つずつ見直すことが大切です。
急激な変化や過剰な対処を避け、ソテツ本来のペースを尊重した育て方が回復の近道となるでしょう。
ポイント
- 日当たり不足が新芽の発生を妨げることがある
- 水や肥料のバランスを見直す必要がある
- 根詰まりが成長を阻害している場合がある
- 環境の急変を避けて、様子を見ながら管理する
ソテツが枯れる理由|葉を全部切る前に復活策を試す

ソテツが枯れかけていると感じたとき、多くの方が真っ先に考えるのが「このまま枯れてしまうのではないか」という不安です。
そして次に浮かぶのが、「すべての葉を切り落として仕切り直した方が良いのでは?」という判断です。
しかし、いきなり葉をすべて切ってしまうのは、かえってソテツにとって大きな負担となる可能性があります。
ソテツが枯れる原因は、単一ではなく複数の問題が重なっているケースが少なくありません。
例えば、水の与えすぎによる根腐れ、日照不足、寒さによるダメージ、長期間の根詰まり、さらには害虫の被害など、どれもが植物にストレスを与える要因となりえます。
これらの原因を正確に把握することが、適切な対処の第一歩です。
葉が黄色くなっていても、根や幹がまだしっかりしていれば、ソテツは復活の見込みがあります。
このため、葉を全部切る前に、まずは環境の改善や管理の見直しといった復活策を講じることが推奨されます。
特に、根の状態をチェックし、過湿であれば水やりを控えたり、必要に応じて植え替えを行ったりすることが有効です。
また、寒さの影響が疑われる場合には、日当たりの良い場所へ移動したり、防寒対策を施すといった対応も有効です。
加えて、害虫が原因である場合は、早期に発見し駆除することも重要なポイントになります。
このように、「葉を全部切る」ことは決して万能な方法ではなく、むしろ復活のチャンスを奪ってしまう可能性もあります。
まずはソテツの状態を冷静に観察し、植物が回復できる余地を最大限に生かすための手立てを試すことが重要です。
枯れてしまったように見えても、適切な対処をすれば再び元気を取り戻すことは十分に可能なのです。
- 丸坊主にする時期の見極め方
- 胴切りでソテツは復活できる?
- 冬にソテツが枯れる理由と対策
- 成長を止める主な原因とは
- 屋外での育て方は?注意するポイント
丸坊主にする時期の見極め方
ソテツの葉をすべて切り落として「丸坊主」にするのは、極端に見えるかもしれませんが、適切なタイミングと方法で行えば、植物の再生を促す手段にもなり得ます。
ただし、葉をすべて落とすことはソテツに大きな負担をかけるため、その判断には慎重さが求められます。
丸坊主にする最適な時期は、気温が安定して暖かくなる春から初夏(おおよそ5月〜6月)とされています。
この時期はソテツの生育が活発になるため、多少のダメージがあっても新芽を出して回復しやすくなります。
逆に、秋や冬に行うと、低温によって成長が止まり、新しい葉を出すエネルギーが不足してしまうため、リスクが高まります。
また、「丸坊主にすべきかどうか」の判断は、葉の状態をしっかり観察したうえで行いましょう。
すべての葉が枯れて茶色くなり、明らかに機能していない場合は、植物が新しい成長を始める準備段階にあるかもしれません。
一方、まだ青く元気な葉が少しでも残っているのであれば、それを維持することで光合成を続け、体力を温存することが可能です。
さらに、丸坊主にした後の管理環境にも注意が必要です。
直射日光に長時間さらすと弱った幹が焼けてしまうこともあるため、半日陰など直射日光を避けた場所で養生させることが重要です。
水やりについても、幹だけの状態では蒸散量が少ないため、水の与えすぎに注意してください。
このように、丸坊主にすること自体は誤りではありませんが、時期・葉の状態・その後の管理の3点を適切に見極めることが、ソテツの健全な再生に繋がります。
ポイント
- 適期は春から初夏の5〜6月頃
- すべての葉が枯れている場合のみ検討する
- 元気な葉が残っていれば切らずに残すべき
- 切った後は直射日光を避けて養生することが重要
胴切りでソテツは復活できる?
ソテツの「胴切り」とは、幹の途中を切断して再発根・再生を促す方法です。
一般的には根腐れや成長停止、虫害などで根や幹が深刻なダメージを受けた際の最終手段として用いられます。
見た目にも大胆なこの処置ですが、条件が整えば、胴切りによってソテツが復活する可能性は十分にあります。
成功させるポイントは、健康な部分をしっかり見極めて切ることです。
幹の下部が黒ずんだり、ブヨブヨしていたりする場合でも、上部がまだ硬くしっかりしていれば、そこから再生を試みることができます。
胴切りを行う際には、清潔でよく切れるノコギリを使用し、断面をできるだけまっすぐに整えることが大切です。
切り口には殺菌剤を塗布するか、数日間日陰で乾燥させてから植え付けを行うと、腐敗のリスクを軽減できます。
植え付け後は、新しい根が出るまで水やりは控えめにし、風通しの良い明るい場所で管理します。
発根までは数か月かかることもあるため、焦らずに経過を見守ることが必要です。
気温が低いと再生がうまく進まないことがあるため、実施する時期は5月〜7月頃が適しています。
一方で、胴切りには失敗のリスクも伴います。
根が再生しなかったり、切り口からカビが発生したりすることもあり得ます。
そのため、胴切りはあくまで通常の方法で改善できなかった場合の最終手段と考えるべきです。
このように、胴切りは高リスクながらも再生の希望をつなぐ方法であり、適切な環境と管理によってソテツの命を救う手段にもなり得ます。
ポイント
- 幹の健康な部分を見極めて切断するのが前提
- 切り口はまっすぐ整え、乾燥・殺菌処理を行う
- 発根まで時間がかかるので水やりは控えめに
- 胴切りは通常の手当で回復できない場合の最終手段
冬にソテツが枯れる理由と対策
冬の間にソテツが元気をなくしたり、葉が黄色く変色したりするのは、珍しいことではありません。
これはソテツが本来、温暖な地域に自生する植物であり、寒さに対してあまり強くないためです。
特に日本の寒冷地では、冬越しの方法によってソテツの健康状態が大きく左右されます。
冬に枯れたように見える主な原因の一つは、低温による生理的なダメージです。
気温が5度を下回るとソテツの代謝が低下し、葉や幹が機能を停止し始めます。
この状態が長期間続くと、見た目には完全に枯れてしまったように見えることもあります。
また、冷たい風や霜が直接当たることで葉が焼けたように変色することも少なくありません。
もう一つの注意点は、冬場の過湿による根腐れです。
気温が低い時期は蒸発量も少ないため、土が乾きにくくなります。
にもかかわらず、通常通りに水やりをしてしまうと、根が水分を吸収できないまま傷んでしまうことがあります。
寒さと湿気が同時に重なると、ソテツにとっては非常にストレスの高い環境になります。
対策としては、まず寒さから守る工夫が不可欠です。
鉢植えであれば、室内や温かい玄関先など、5度以上を保てる場所に移動させるとよいでしょう。
地植えの場合は、幹の部分を藁や不織布などで包み、冷気や霜を直接受けないように保温対策を施します。
また、水やりの頻度も調整が必要です。
基本的には土の表面が完全に乾いてからごく少量を与える程度にとどめ、土が常に湿っている状態は避けましょう。
さらに、肥料も冬の間は与えないことが望ましく、成長期まで控えることで根の負担を減らすことができます。
このように、冬場の管理は「寒さ」と「湿気」のバランスが鍵になります。
事前の準備と注意深い観察によって、ソテツが無事に春を迎えられるようサポートすることが大切です。
ポイント
- 気温5度以下になると代謝が落ちて枯れたように見える
- 冷たい風や霜で葉が変色・ダメージを受けることがある
- 過湿により根腐れを起こしやすい時期でもある
- 室内への移動や幹の保温で寒さ対策を行う
成長を止める主な原因とは
ソテツが長いあいだ成長しない、あるいは新芽が出ないという状況が続く場合、何らかの原因によって植物の生理活動が妨げられている可能性があります。
こうした停滞は放置すると、そのまま弱って枯れてしまうリスクもあるため、できるだけ早い段階で原因を見極めることが大切です。
まずよく見られる原因のひとつが、根の問題です。
ソテツは根がしっかりと土中に張り巡らされることで、十分な水分と栄養を吸収し、成長を続けることができます。
しかし、長年植え替えをしていない鉢植えでは、根が鉢いっぱいに広がって「根詰まり」を起こしてしまい、必要な栄養が行き渡らなくなります。
また、過湿な環境では根腐れを起こして機能を失い、成長が止まる要因にもなります。
次に注目すべきなのが日照不足です。
ソテツは本来、強い光を好む植物ですので、日当たりの悪い場所に置かれていると光合成が十分に行われず、成長のエネルギーが不足してしまいます。
特に新芽が出にくくなったり、葉の色が薄くなったりする場合は、設置場所の見直しが必要です。
さらに見逃せないのが気温の影響です。
ソテツの活動が活発になるのはおおむね15度以上であり、寒冷な気候では生育が鈍ります。
冬場に成長が止まるのは自然な反応ですが、春以降になっても回復しない場合には、寒さによるダメージが長引いている可能性があります。
加えて、肥料の過不足も成長を妨げる原因になります。
栄養が極端に不足していれば新芽を出す力がなくなりますし、逆に与えすぎると根が傷むこともあるため、適切な量とタイミングで与えることが求められます。
このように、ソテツの成長が止まる背景には、根の状態、日照、気温、栄養など、さまざまな要因が複雑に関係しています。
それぞれの環境条件を見直しながら、問題を一つずつ取り除いていくことで、再び元気に成長を始める可能性が高まります。
ポイント
- 根詰まりや根腐れで栄養吸収が妨げられる
- 日照不足により光合成が不十分になる
- 気温が低すぎると生育が鈍る
- 肥料の過不足も成長の停滞を招く
屋外での育て方は?注意するポイント
ソテツは丈夫な植物として知られており、日本でも庭木として屋外で育てられるケースが少なくありません。
しかし、丈夫さゆえに管理が簡単だと誤解されやすく、間違った育て方によって枯れてしまうこともあります。
屋外栽培では特に、環境変化の影響を受けやすいため、いくつかの注意点を押さえる必要があります。
まず最も重要なのが植える場所の日当たりです。
ソテツは南国原産の植物であるため、直射日光を好みます。
日陰が多い場所では光合成が不十分となり、葉が黄色くなったり、新芽の成長が遅れたりすることがあります。
できるだけ1日を通してよく日が当たる場所を選ぶとよいでしょう。
次に気をつけたいのが水はけの良さです。
地植えであっても、排水性の悪い土壌では雨水が溜まりやすくなり、根腐れのリスクが高まります。
もし粘土質の土であれば、植える前に砂や腐葉土を混ぜて、通気性と排水性を高めておくと安心です。
梅雨の時期や長雨が続いた際には特に注意が必要です。
また、気温の変化に対する対策も大切です。
ソテツは耐寒性がそれほど高くないため、特に冬の寒冷地では凍結や霜にさらされるとダメージを受けやすくなります。
寒さが厳しい地域では、幹の部分を藁や不織布などで保温したり、根元をマルチングして土の温度を保つ工夫をしておくと、冬越しがしやすくなります。
さらに、屋外では害虫の被害にも注意が必要です。
ソテツにはソテツシジミの幼虫がつきやすく、これが葉を食べてしまうことで、見た目が損なわれるだけでなく成長に支障をきたすこともあります。
定期的に葉の裏や株元を観察し、初期の段階で発見・除去できるよう心がけましょう。
屋外でソテツを健やかに育てるためには、「日光・水はけ・寒さ対策・害虫管理」の4点が特に重要です。
これらの条件を整えたうえで、定期的な観察とメンテナンスを怠らなければ、ソテツは季節を問わず、美しい葉を保ち続ける頼もしい植物になります。
ポイント
- 日当たりが良い場所で管理することが基本
- 水はけの良い土壌でないと根腐れの原因になる
- 寒冷地では防寒対策が必須になる
- 害虫被害にも注意し、葉の裏などを定期的に観察する
-

-
庭タープのおすすめ13選!支柱や張り方も紹介|庭ASOBI
本記事はプロモーションが含まれています 庭に張るタープのおすすめ13選と支柱・張り方・重り活用まで【完全解説】 庭に張るおすすめのタープを探している方にとって、どのタイプを選べばよいか迷うのは当然のこ ...
続きを見る
【まとめ】ソテツが枯れる原因!葉を全部切る前に見直すポイント
ソテツが枯れているように見える場合、すぐに葉を全部切ってしまうのではなく、まずは枯れの原因を冷静に見極め、必要に応じた対処を行うことが大切です。
この記事のまとめ
- 葉の黄変だけでは枯れているとは限らない
- 水のやりすぎで根腐れを起こしていることがある
- 地植えでは自然の雨で育つため水やりは控えめにする
- 冬場は5度以下の寒さでダメージを受けやすい
- 寒冷地では幹の保温や室内への移動が効果的
- 鉢植えでの長期栽培は根詰まりの原因になる
- 植え替えは根の状態を見てタイミングを図る
- カイガラムシやソテツシジミの被害も成長を妨げる
- 葉の裏や茎周辺の定期的な観察が予防につながる
- 健康な葉は残して光合成による回復力を保つ
- 剪定は時期と方法を誤るとソテツが弱る原因になる
- 根腐れの判断には葉と根の両方の観察が必要
- 排水性の悪い土壌は根への酸素不足を招きやすい
- 土の湿り具合や臭いも根の状態確認に役立つ
- 枯れの原因は複数重なる場合もあるため総合的に判断する
この記事で紹介したように、ソテツが枯れてしまった。葉を全部切れば復活する?そう思う前には、見た目だけで判断せず、植物の状態を丁寧に見極めることが肝心です。
焦らず、適切な環境とケアを施せば、ソテツは元気を取り戻す可能性があります。
-

-
庭にソテツをおしゃれに植える!映える配置と育て方の極意32選
本記事はプロモーションが含まれています 庭にソテツをおしゃれに!配置・育て方・剪定の基本まとめと32のテクニック 南国風の雰囲気を手軽に演出できる植物としては人気のソテツは、その独特な存在感から「庭に ...
続きを見る
-

-
ソテツの新芽が出ない原因と対策10選|育て方のコツとは
本記事はプロモーションが含まれています ソテツの新芽に関する悩みを解消|出ない・伸びすぎ・茶色への対応完全ガイド 「ソテツの新芽が出たら何をすればよいのか?」「新芽が出ない場合はどう対処すればよいのか ...
続きを見る
