本記事はプロモーションが含まれています

「庭の芝生をタイルに変えたい…」
上記のような悩みを抱える人の多くは、芝生の管理に疲れ、もっと手入れの少ない庭づくりを検討しているのではないでしょうか。
見た目の美しさは魅力でも、芝生は雑草取りや水やり、定期的な刈り込みなど、維持に手間と時間がかかります。
「庭の芝生をやめたい…」
と感じたとき、選択肢として浮かぶのが、タイル・砂利・レンガ・人工芝などへの切り替えです。
なかでも、庭を芝生からタイルに変更する方法は、見た目の整った印象とともに、長期的に手入れが楽になる点で支持されています。
このページでは、芝生をやめてタイルにDIYで施工する方法や、芝生の上にタイルを敷く際の注意点、さらには芝生をやめてレンガや砂利を使う際の比較ポイントについても解説していきます。
また、芝生をやめたあとの準備として重要な整地・防草処理の考え方や、芝生を剥がす費用はいくら?といった疑問への目安も紹介します。
さらに、庭の仕上がりや予算に直結する「コンクリートとタイルのどちらが安い?」という比較ポイントも押さえています。
手入れのいらない庭をDIYで叶えたいと考えている方に向けて、素材選びから施工方法、費用の目安までを網羅的にお届けします。
初めての方でも分かりやすく、失敗しない庭づくりのための情報をまとめました。
この記事を読むポイント
- 芝生をやめる理由と日常管理の悩み
- タイルに変えるための具体的な準備と手順
- タイル・砂利・レンガなど代替素材との比較
- DIYや業者依頼時の費用や注意点
-

-
庭の芝生をやめたい人必見|手入れ不要に変える7つの方法|庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 芝生のある庭に憧れて張ってみたものの、 「手入れが大変」「放置するとすぐに荒れる」「管理の負担が大きい」 このように感じている方は少なくありません。 この記事に ...
続きを見る
庭を芝生からタイルにする基本情報

芝生のある庭は見た目に美しく、季節の移ろいを感じられる点が魅力です。
しかしその一方で、手入れに時間と労力がかかることから、維持を続けるのが難しいと感じる人も少なくありません。
そんな背景から、近年では芝生を撤去してタイルを敷くという選択が注目を集めています。
タイル敷きの庭は、雑草が生えにくく、土のようにぬかるむ心配もありません。
そのため、日々の手入れが大幅に減り、見た目も整った空間を長く保ちやすいというメリットがあります。
また、タイルにはさまざまな種類があり、デザイン性にも優れているため、好みに応じた庭づくりが可能です。
耐久性が高い素材を選べば、長期間にわたってメンテナンスの手間を抑えることができます。
ただし、芝生をタイルに変えるには、単に上から敷くだけでは済みません。
適切な下地処理や整地、防草対策といった準備が必要となり、それに伴って費用や作業工程も発生します。
どのような素材を使い、どの範囲をタイル化するのかによって、必要な工程や費用は大きく異なってきます。
ここでは、芝生からタイルへ変更する際に知っておくべき基本的な情報を解説していきます。
具体的な施工方法や必要な準備、DIYと業者依頼の違いなど、初めての方でも分かりやすく理解できるよう、順を追って説明していきます。
- 庭の芝生をやめたい人の悩みとは
- 芝生をやめたあとにやるべき準備とは
- 芝生を剥がす費用はいくら?目安を解説
- 芝生の上にタイルは敷ける?注意点まとめ
庭の芝生をやめたい人の悩みとは
庭の芝生をやめたいと感じる人は、見た目の問題だけでなく、日常の管理やコストに関する複数の悩みを抱えていることが多いようです。
特に多く挙げられるのが、定期的な草刈りや水やりなど、芝生の維持にかかる手間と時間です。
春から秋にかけては成長が早く、頻繁な手入れが求められるため、共働き家庭や高齢者には大きな負担となります。
また、雑草の発生も見逃せない問題です。
芝の間から雑草が生えてくると見た目が悪くなるだけでなく、雑草取りにも時間と労力がかかります。
さらに、ペットや小さな子どもがいる家庭では、農薬や除草剤の使用にも慎重にならざるを得ません。
芝生の美しさを保つには、専用の肥料を使ったり、エアレーション(通気)といった管理も必要になります。
こうした専門的なメンテナンスを継続するのが難しいと感じ、
「維持しきれないならいっそ撤去したい…」
と考える人が増えているのです。
さらに、芝生の張り替え費用や再生処置にもコストがかかる点も悩みの一つです。
一時的には緑がよみがえっても、数年後にはまた同じ状態になり、繰り返しの出費につながるため、経済的な面でも見直しが進んでいます。
このような背景から、
「庭はもっと楽に、見栄えよく保ちたい」
「もっと実用的なスペースにしたい」
上記のようなニーズが高まり、芝生の代替としてタイルや砂利、人工芝などが選ばれるようになっています。
管理の負担を軽減しつつ、美観を保ちたいというのが、芝生をやめたいと考える人の大きな動機といえるでしょう。
ポイント
- 草刈りや水やりなどの手入れが頻繁で大変
- 雑草が生えやすく見た目も悪化しやすい
- 子どもやペットがいると農薬使用に気を遣う
- 維持費や張り替え費用が継続的にかかる
芝生をやめたあとにやるべき準備とは
芝生をやめてタイルや他の素材に変えると決めた場合、ただ芝を剥がすだけでは理想の庭にはなりません。
美しい仕上がりと長期的な維持を目指すためには、事前の準備が非常に重要です。
まず初めに行うべきは、現在の芝生を丁寧に撤去する作業です。
根ごとしっかりと掘り起こすことで、後々の雑草の再発を防ぐ効果が期待できます。
その後、地面の高さや傾斜を確認しながら整地作業に移ります。
この段階で不要な凹凸や水はけの悪い部分を改善しておかないと、タイルを敷いた後に不陸(でこぼこ)や水たまりの原因となることがあります。
場合によっては土を入れ替えたり、転圧機で地面をしっかり固めたりといった工程も必要になります。
整地が終わったら、雑草の再発を防ぐために防草シートを敷くのが一般的です。
このシートは太陽光を遮断して雑草の発芽を抑えるもので、タイルや砂利の下に敷くことで長期間メンテナンスの手間を軽減する効果があります。
防草シートを敷く際は、重なり部分がずれないようしっかりと固定することが重要です。
さらに、タイルや他素材の設置前には、使用する素材の種類に応じた下地作りも必要です。
例えば、コンクリートタイルの場合はモルタルでしっかり固定する必要がありますし、ジョイントタイルや人工芝を使う場合は、ある程度の平らな地面が求められます。
芝生の撤去から整地、防草対策、下地準備まで、手順を省かず丁寧に進めることで、仕上がりの美しさと後々の管理のしやすさが大きく変わってきます。
こうした準備をしっかり行うことが、タイル敷きの成功と長持ちに直結するのです。
ポイント
- 芝生を根から丁寧に撤去して雑草を防ぐ
- 地面を平らに整地して水はけも確認する
- 防草シートを敷いて草の再発を防止する
- 使用素材に合わせた下地を整えることが重要
芝生を剥がす費用はいくら?目安を解説
芝生を剥がす費用は、庭の広さや作業方法、依頼する業者によって大きく異なります。
一般的な目安として、1㎡あたり1,000円〜3,000円前後が相場です。
この価格には、芝生の撤去作業・処分費・人件費などが含まれます。
ただし、土の掘削が必要な場合や、大量の根が張っている芝生を手作業で取り除く場合には、さらに費用が上乗せされることがあります。
例えば、20㎡の庭で芝生を完全に剥がす場合、最低でも2万円、条件によっては6万円以上かかることもあるため、事前に見積もりを取ることが大切です。
また、芝生の種類や状態によっても難易度が異なります。
高密度で深く根を張っている芝生は、表面だけを剥がすのが難しく、重機を使った作業が必要になるケースもあるため、結果的に費用が高くなる傾向があります。
DIYで作業を行えば、費用を大幅に抑えることも可能です。
スコップや草削り、根切り鎌などの道具があれば、自力での撤去も現実的です。
ただし、労力と時間はかなりかかります。
特に広い庭の場合、作業の負担は想像以上になることが多いため、自身の体力やスケジュールと相談しながら進める必要があります。
処分費についても注意が必要です。
剥がした芝生や根、土の処分には自治体のルールがあり、粗大ごみとして回収されない場合や、専門の業者に依頼しなければならないこともあります。
処分費用は1袋あたり500円〜1,000円前後が一般的ですが、大量の場合は別途トラックでの回収費が加算されるケースもあります。
このように、芝生を剥がす費用は単純な作業代だけでなく、廃材の処分や追加作業の有無によって変動します。
最終的な金額は現場の状況次第で変わるため、複数の業者から見積もりを取り、内容をしっかり比較することが安心につながります。
ポイント
- 相場は1㎡あたり1,000〜3,000円程度
- DIYなら費用を抑えられるが労力がかかる
- 状況により処分費や重機費が加算される
- 芝の状態によっては費用が大きく変動する
芝生の上にタイルは敷ける?注意点まとめ
芝生の上に直接タイルを敷くことは一見簡単な方法に見えますが、長期的な視点から見ると、あまりおすすめできません。
その理由は、芝生が生きている状態では時間とともにタイルが浮いたり、傾いたりする可能性が高いためです。
芝の成長による地面の変化や水分の保持などが、タイルの安定性に影響を及ぼします。
特にジョイントタイルや樹脂製タイルのような軽い素材は、下地が不安定な状態だとズレやすく、歩行中にガタつきが発生することがあります。
これにより、つまずきや転倒の原因となるほか、見た目の美しさも損なわれてしまいます。
また、芝の上にそのままタイルを敷くと、芝が死滅しない限り、隙間から新しい芽が伸びてくることがあります。
これが見栄えを悪くするだけでなく、再び雑草のように管理が必要な状態になってしまうため、本来の「手入れ不要な庭」という目的が果たせなくなってしまいます。
そのため、芝生を完全に撤去し、防草シートなどを敷いたうえでタイルを設置する方法が推奨されます。
地面をしっかりと整地しておくことで、タイルの沈み込みやズレを防ぎ、より長持ちする仕上がりになります。
防草シートは日光を遮断し、植物の成長を抑制する効果があるため、雑草対策としても有効です。
一方で、
「とりあえず一時的に見た目を変えたい」
「DIYで簡易的に設置したい」
上記のような目的であれば、芝生の上にタイルを敷くことも不可能ではありません。
その場合は、タイルの下にプラスチックパネルを敷いたり、水平を保つための下地材を使ったりするなど、できるだけズレを抑える工夫が必要です。
いずれにしても、芝生の上にタイルを敷くかどうかは、目的や使用期間、予算によって判断することが重要です。
見た目の美しさだけでなく、安全性やメンテナンス性も考慮したうえで、最適な施工方法を選びましょう。
ポイント
- 芝の上に直接敷くとタイルがズレやすい
- 地面の変化でタイルが傾くリスクがある
- 雑草や芝が隙間から再び生えてくる恐れがある
- 本施工には芝の撤去と防草処理が必要
-

-
庭を芝生以外にしたい!プロがすすめる代替素材ベスト5 | 庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 芝生は見た目に美しい一方で、芝刈りや水やり、雑草取りなど、日々のメンテナンスに手間がかかる点が課題です。 「庭の芝生をやめたい…」と感じている方にとって、芝生の ...
続きを見る
庭を芝生からタイルに変える際の比較と選択

庭の芝生をタイルに変える際には、複数の素材や工法から自分にとって最適な選択をすることが大切です。
ただ見た目を変えるだけでなく、その後の使い勝手やメンテナンス、さらには施工にかかるコストや手間まで含めて検討する必要があります。
タイルと一口にいっても、コンクリートタイル・磁器タイル・ジョイントタイルなど、用途や予算に応じて多様な選択肢があります。
また、芝生の代替素材としては、タイル以外にも砂利やレンガ、人工芝なども存在し、それぞれ異なるメリット・デメリットを持っています。
例えば、タイルはフラットで掃除がしやすく、雑草の発生を抑えやすいのが特徴ですが、初期費用が高くなりがちです。
一方、砂利は費用を抑えつつDIYでも施工しやすい素材ですが、歩行性や掃除のしやすさでは劣ることがあります。
レンガはデザイン性に優れ温かみのある雰囲気を演出できますが、敷設にやや手間がかかるという側面もあります。
これらの素材ごとの特徴を比較し、自分の庭に合った素材を選ぶことが、快適で長持ちする庭づくりへの第一歩となります。
この章では、芝生をやめてタイルに変える際に考慮すべき素材選びや施工方法の違いについて詳しく見ていきます。
デザイン性・コスト・耐久性など、多角的な視点から比較しながら、後悔のない選択をするための情報を提供していきます。
- 芝生をやめてタイルに!DIYでの施工方法
- 庭の芝生をやめる砂利との比較ポイント
- 芝生をやめてレンガという選択肢も
- 手入れのいらない庭に!DIYで叶える方法
- コンクリートとタイルのどちらが安い?
芝生をやめてタイルに!DIYでの施工方法
芝生をやめてタイルに変える方法は、プロに依頼しなくてもDIYで対応できるケースがあります。
特に最近では、施工が簡単なジョイントタイプのタイルが数多く販売されており、道具と手順さえ理解していれば、初心者でも比較的スムーズに仕上げることが可能です。
ただし、美観や耐久性を重視する場合には、下地処理を丁寧に行うことが重要になります。
まず取りかかるべきなのは、芝生の撤去作業です。
芝をスコップなどで根から剥がし、地面を平らに均しておきます。
このとき、小石や根っこの残骸を丁寧に取り除いておくと、仕上がりが美しくなるだけでなく、タイルのズレや浮き上がりを防ぐことにもつながります。
必要であれば土を追加したり、転圧機で固めることで、タイルの沈み込みを防止できます。
その次に行うのが防草シートの敷設です。
防草シートは雑草の再発を防ぎ、タイルの隙間から草が生えてくるのを防止する役割を果たします。
防草シートはタイルの下にしっかりと敷き、端部はピンなどで固定しておくと安心です。
そして、いよいよタイルの設置に移ります。
ジョイントタイルの場合、並べてパチッとはめていくだけの簡単な作業ですが、タイルの配置バランスや隙間の均一さを意識すると仕上がりが格段に良くなります。
特に角や端の処理では、必要に応じてタイルをカットする場面もあるため、カッターやタイルカット用の工具を準備しておくと便利です。
DIYの最大の魅力は、コストを抑えつつ、自分の好みに合ったデザインに仕上げられる点です。
ただし、水平調整や排水性などを考慮せずに施工すると、雨水が溜まる・歩きにくいといったトラブルにつながることもあるため、下地づくりを怠らないことが成功の鍵になります。
初めての人でも、工程を一つひとつ丁寧に行えば、機能的で見た目も美しいタイル敷きの庭が実現できます。
ポイント
- 芝を撤去して地面を平らに整えることが第一歩
- 雑草対策に防草シートを必ず敷く
- ジョイントタイルはDIY初心者にも扱いやすい
- 端や角の処理は丁寧に行い見た目を整える
庭の芝生をやめる砂利との比較ポイント
芝生の代わりにタイルを敷くか、それとも砂利にするかは、庭の使い方やメンテナンスの手間、そしてデザインの好みによって大きく変わってきます。
どちらにも利点と注意点があるため、それぞれの特徴をしっかり把握したうえで選ぶことが大切です。
まず、タイルは見た目が整っており、デザイン性が高い点が大きな魅力です。
表面が平らで掃除もしやすく、ウッド調や石目調など種類も豊富にあります。
そのため、スタイリッシュなエクステリアを求める方や、テラスやベンチを設置したい人に向いています。
また、耐久性が高く、長期間にわたって美しい状態を保てるのも特徴です。
一方で、砂利は施工が比較的簡単で、費用もタイルより抑えられる傾向があります。
材料費と人件費の総額で見ると、タイルの半分程度に収まるケースも珍しくありません。
さらに、砂利は防犯対策にもなります。
歩くと音が鳴るため、敷地内への侵入を気づきやすくなるのです。
ただし、歩くと不安定だったり、靴に小石が挟まったりする点は、使い方によってはデメリットになる可能性があります。
メンテナンス面では、タイルは雑草が生えにくく、掃除も箒で簡単に済ませられます。
対して砂利は、雑草が混じりやすく、防草シートを敷かないと定期的な草むしりが必要になることもあります。
また、砂利が雨風で流れたり、歩行で散らばることもあるため、定期的な補充や整え直しも必要です。
このように比較すると、砂利はコスト重視や施工の手軽さを求める人向き、タイルは見た目と機能性を重視する人向きという傾向があります。
庭をどう活用したいか、どこまで管理に手をかけられるかを整理したうえで、自分に合った素材を選ぶことが失敗のない選択につながります。
ポイント
- 砂利はタイルより施工費が安く済みやすい
- 歩くと音が出るため防犯面でも有利
- 雨や風で砂利が流れたり散らばることがある
- 見た目と耐久性はタイルの方が優れている
-
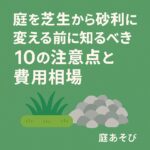
-
庭を芝生から砂利に変える前に知るべき10の注意点と費用相場|庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 庭を芝生から砂利に変えたいと考えている方の中には、 「手入れが大変」「芝生をやめるべきか迷っている」 このように感じている方も多いのではないでしょうか。 この記 ...
続きを見る
芝生をやめてレンガという選択肢も
芝生をやめてタイルや砂利以外にもう一つ注目されている素材が「レンガ」です。
温かみのある見た目とナチュラルな雰囲気が魅力で、洋風の庭やカフェ風ガーデンを目指す方には特に人気があります。
施工の自由度が高く、並べ方次第でさまざまなデザインを演出できるのも大きな特徴です。
レンガは吸水性が高く、雨が降っても水たまりになりにくいという特性があります。
また、滑りにくいため、小さな子どもや高齢者が歩く庭でも安心して使えます。
色味も赤系から茶系、グレー系まで幅広く、既存の外構や住宅の雰囲気に合わせやすい点も使いやすさのひとつです。
施工方法はタイルと似ていて、整地→防草シート→下地(砂やモルタル)→レンガ設置という流れになります。
DIYで取り組むことも可能ですが、均一に敷き詰めるには地面の水平調整が欠かせません。
特に曲線や段差を取り入れたデザインにする場合は、多少の技術や道具が必要になるため、慎重に進める必要があります。
ただし、レンガは経年変化により表面にコケがついたり、色がくすんだりすることもあります。
これを「味」として楽しむ人もいれば、見た目が劣化したと感じる人もいます。
また、レンガ同士の隙間から草が生えてくる可能性もあるため、目地部分の管理も忘れてはいけません。
このように、レンガは雰囲気のある仕上がりと歩きやすさ、排水性の良さを備えた選択肢ですが、やや手間がかかる素材でもあります。
おしゃれさと実用性のバランスを見ながら、施工の難易度や長期的なメンテナンスも踏まえて検討するのが賢明です。
ポイント
- レンガはナチュラルで温かみのある雰囲気にできる
- 吸水性が高く滑りにくい特性がある
- 経年変化やコケで見た目が変わることがある
- 敷き方や曲線設計には技術と手間が必要
手入れのいらない庭に!DIYで叶える方法
手入れのいらない庭を実現したいと考える人が増えています。
雑草の処理や芝生のメンテナンスに追われる生活から解放されたいという声は特に多く、時間的にも精神的にも余裕を持ちたい方にとって、庭の手間を減らすことは大きな課題です。
そこで注目されているのが、DIYによる庭の簡素化・低維持管理化です。
まず検討すべきは、庭全体の素材選びです。
芝生を撤去したあと、タイルや人工芝、防草シート+砂利といった組み合わせを活用することで、日常的な手入れを大幅に減らせます。
中でもジョイントタイルは、はめ込むだけで設置できるため、DIY初心者でも手軽に扱えます。
土の上に敷く場合は、防草シートと併用することで雑草の発生を抑制できるため、ほとんどメンテナンス不要な状態をつくることが可能です。
さらに、庭の設計にあらかじめ水はけのよい構造を取り入れることで、雨が降った際にぬかるみができにくくなり、日々の清掃も楽になります。
例えば、傾斜をつける、砂利層を設けて水を地中に逃すといった工夫は、外観を損ねずに実用性を高める手法です。
また、植栽を一部に限定して配置する方法も有効です。
あえて花壇やプランターなど「管理がしやすい範囲だけ」に植物を置くことで、緑のある空間を保ちつつ、広範囲の手入れを避けられます。
このとき、自動散水機などを組み合わせることで、水やりの手間も軽減できます。
手入れのいらない庭は、何もすべてを人工素材で固める必要はありません。
自然素材とうまく付き合いながら、自分の生活スタイルに合ったDIYの工夫を取り入れることが、心地よい庭づくりの第一歩です。
準備段階から計画的に進めれば、快適かつ省力な庭は誰にでも実現可能です。
ポイント
- 防草シートとジョイントタイルの組み合わせが効果的
- 水はけの良い構造をあらかじめ設計するとよい
- 植物を限定的に配置すれば管理しやすい
- 自動散水機などで手間をさらに減らせる
コンクリートとタイルのどちらが安い?
コンクリートとタイルのどちらが費用を抑えられるかは、施工面積や工法、使用目的によって変わります。
ただ、一般的な傾向としては、単純な床材として施工する場合はコンクリートの方が安価になりやすいというのが多くの業者やDIYユーザーの意見です。
コンクリートは材料費が比較的安く、広範囲に一気に打設できる点がコストパフォーマンスに優れています。
1㎡あたりの施工費は5,000円〜8,000円が目安とされており、下地整備や型枠を含めても費用の上昇幅は緩やかです。
また、雑草が生えにくく、耐久性も高いため、維持費も抑えられるという利点があります。
一方、タイルは素材の種類によって価格にばらつきが大きく、安価なものなら1㎡あたり5,000円程度、高級なタイルでは1万円以上になることもあります。
さらに、タイルは1枚ずつ丁寧に設置する必要があるため、施工費が高くなる傾向があります。
とくに複雑なデザインやカット加工が必要な場合、作業時間も長くなり、人工代がかさみます。
とはいえ、タイルにはタイルならではの魅力があります。
デザイン性の高さ、カラーバリエーション、滑りにくい表面加工など、見た目と機能性を両立できる素材です。
また、タイルの種類によっては断熱性があるため、夏場の照り返しが抑えられる効果も期待できます。
コスト面を重視するならコンクリートが有利ですが、見た目や質感、デザインにこだわりたい場合はタイルを選ぶ価値があります。
どちらを選ぶかは、「予算内でどこまでの仕上がりを求めるか」という点で判断するのがよいでしょう。
見積もりを複数取り、長期的な維持費も含めて総合的に比較することが、後悔のない選択につながります。
ポイント
- 一般的にはコンクリートの方が費用は安い
- タイルは施工手間がかかり費用が上がりやすい
- タイルはデザイン性や表面加工で選ばれる傾向がある
- 維持費まで含めた総合的な比較が必要
-
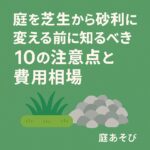
-
庭を芝生から砂利に変える前に知るべき10の注意点と費用相場|庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 庭を芝生から砂利に変えたいと考えている方の中には、 「手入れが大変」「芝生をやめるべきか迷っている」 このように感じている方も多いのではないでしょうか。 この記 ...
続きを見る
-

-
庭にソテツをおしゃれに植える!映える配置と育て方の極意32選
本記事はプロモーションが含まれています 庭にソテツをおしゃれに!配置・育て方・剪定の基本まとめと32のテクニック 南国風の雰囲気を手軽に演出できる植物としては人気のソテツは、その独特な存在感から「庭に ...
続きを見る
【まとめ】庭を芝生からタイルに変える前に知るべきこと

芝生の庭は美観に優れていますが、維持管理の手間やコストに悩む方が増えています。
こうした背景から、より管理がしやすく機能的な「タイル」へのリフォームが注目されています。
ここでは、庭を芝生からタイルに変える際に押さえておきたい要点を総まとめとしてご紹介します。
この記事のまとめ
- 芝生の管理には草刈り・水やり・肥料など多くの手間がかかる
- 高齢者や多忙な家庭には芝生の維持が大きな負担になる
- 雑草対策や除草剤の使用に悩む家庭も少なくない
- 美観を維持するには定期的な芝の張り替えが必要になる
- 芝の再生にも費用がかかり、繰り返すと経済的負担が増える
- 芝生の撤去後は整地や防草対策など入念な準備が必要
- タイルの施工前には防草シートで雑草を防ぐのが効果的
- 芝生の上に直接タイルを敷くと不安定になりやすい
- DIYでもタイル敷きは可能だが、下地づくりが成功の鍵
- タイルは掃除がしやすく長期間きれいな見た目を保ちやすい
- 砂利はコストを抑えやすく防犯性もあるが、散らばる点に注意
- レンガはデザイン性に優れるが、管理と施工にやや手間がかかる
- 手入れのいらない庭にするには素材選びと排水設計が重要
- コンクリートは初期費用を抑えやすく、雑草対策にも効果的
- タイルは見た目と耐久性を重視したい人に適している
芝生をタイルに変えるという選択は、庭を「ラクに・美しく・実用的に」保つための有効な手段です。
作業工程や素材の特徴を理解し、自分の生活スタイルに合った庭づくりを計画的に進めることが、後悔のないリフォームへの第一歩となるでしょう。
芝生からタイルに変える前に知っておきたい10の注意点
- 芝生は根まで丁寧に撤去しないと再生してしまう
- 整地をしっかり行わないとタイルが沈んだり水たまりの原因になる
- 防草シートは雑草対策に必須で、施工の長持ちにもつながる
- 芝生の上に直接タイルを敷くとズレや浮きが生じやすくなる
- DIY施工では下地作りを丁寧に行わないと仕上がりに差が出る
- 費用は撤去や処分、道具代、労力も含めて見積もる必要がある
- 排水性と安全性の確保も忘れずに考慮することが大切
-

-
庭の芝生をやめたい人必見|手入れ不要に変える7つの方法|庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 芝生のある庭に憧れて張ってみたものの、 「手入れが大変」「放置するとすぐに荒れる」「管理の負担が大きい」 このように感じている方は少なくありません。 この記事に ...
続きを見る
-
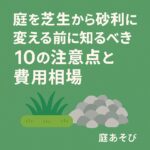
-
庭を芝生から砂利に変える前に知るべき10の注意点と費用相場|庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 庭を芝生から砂利に変えたいと考えている方の中には、 「手入れが大変」「芝生をやめるべきか迷っている」 このように感じている方も多いのではないでしょうか。 この記 ...
続きを見る
-

-
庭を芝生以外にしたい!プロがすすめる代替素材ベスト5 | 庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 芝生は見た目に美しい一方で、芝刈りや水やり、雑草取りなど、日々のメンテナンスに手間がかかる点が課題です。 「庭の芝生をやめたい…」と感じている方にとって、芝生の ...
続きを見る
芝生からタイルに変えたい際にあるよくある質問(FAQ)
-
芝生を剥がさずにタイルを敷いても本当に大丈夫?
-
一時的な見た目の変更なら可能ですが、長期的にはおすすめできません。
芝生が伸びたり腐ったりするとタイルが浮き、傾きやガタつきの原因になります。
また隙間から雑草のように芝が生えてくるため、結果的に手入れが必要になります。本施工する場合は「芝撤去 → 整地 → 防草シート → タイル」の手順が必須です。
-
DIY初心者でもタイル敷きは失敗せずにできる?
-
可能ですが、最も難しいのは“下地づくり”です。
地面がデコボコのままタイルを敷くと、沈み込みや不陸が起き、後悔につながります。初心者が失敗しやすいポイントは
- 地面の水平が取れていない
- 転圧不足で地盤が柔らかい
- 防草シートが適切に固定されていない
など。
特に広範囲の場合は、部分的に業者へ下地だけ依頼する人も増えています。
-
砂利・レンガ・タイル…結局どれが一番ラクで長持ち?
-
“ラクさ”を最優先するなら タイル ≧ コンクリート > 砂利 > レンガ という傾向があります。
素材 手入れ 耐久性 コスト タイル 草が生えにくく掃除も簡単 高い やや高い コンクリート 草ほぼなし 最高 安い 砂利 シート必須で草が生えやすい 中〜低 安い レンガ 目地から草が出やすい 中 中 見た目と実用性のバランスを重視する人は タイル
低コストと雑草対策を重視する人は コンクリート が向いています。
-
芝生の撤去ってどれくらい大変?自分でやるべき?
-
20㎡をDIYすると、丸1〜2日かかることが一般的です。
根が深いタイプだとさらに重労働になります。DIYのハードル
- 土や芝の処分量が多い
- 根の除去が重たい
- 地面の均しに時間がかかる
費用を抑えたい気持ちはあっても、「芝撤去だけ業者に依頼」する人がとても多いのは、この作業が最も大変だからです。
-
DIY費用と業者費用、どれくらい差が出る?
-
目安は以下です。
◆ DIYの場合(材料費のみ)
- 芝撤去:ほぼ無料(処分費は別途必要)
- 防草シート:1㎡あたり300〜600円
- ジョイントタイル:1㎡あたり2,000〜6,000円
→ 合計:1㎡あたり 2,500〜6,000円程度
◆ 業者の場合
- 芝撤去:1㎡あたり1,000〜3,000円
- タイル施工:1㎡あたり10,000円前後
→ 合計:1㎡あたり 12,000〜15,000円が目安
施工範囲が広いほど差が大きくなるため、節約目的でDIYを選ぶ人は多いです。
