本記事はプロモーションが含まれています
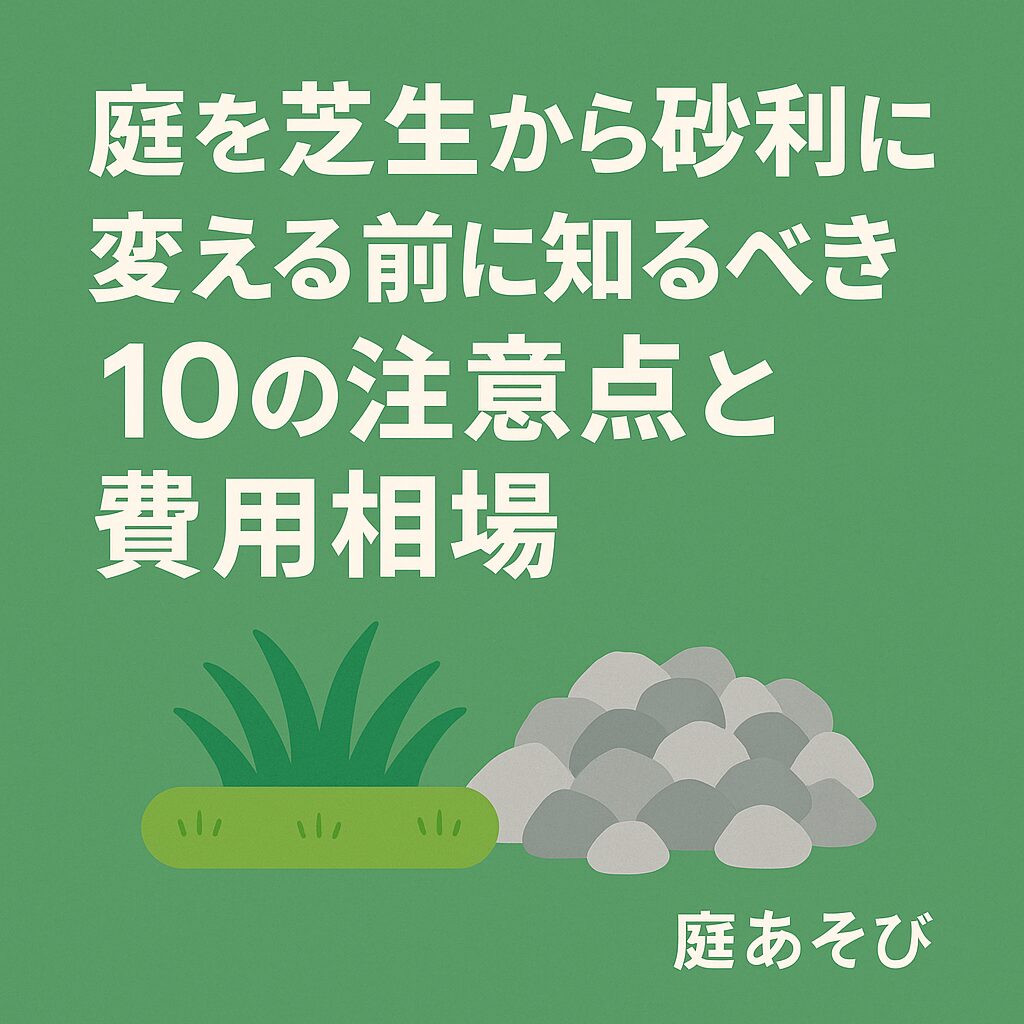
庭を芝生から砂利に変えたいと考えている方の中には、
「手入れが大変」
「芝生をやめるべきか迷っている」
このように感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、砂利に変える際の費用相場やDIYの手順、境界の仕上げ方、さらには人工芝と砂利を組み合わせた庭のアイデアまで幅広く解説しています。
芝生は見た目の美しさこそありますが、成長期の芝刈りや雑草対策など、日々の手入れが大きな負担になることもあります。
そうした背景から「庭の芝生をやめる」という選択肢を検討する家庭も増えてきました。
特に、防草シートと砂利を組み合わせる方法は、維持管理がラクでデザイン性も高く、忙しいご家庭や高齢の方にもおすすめです。
また、庭の雰囲気をより洗練されたものにしたい場合は、タイルを取り入れたデザインや、砂利の上に天然芝を部分的に活用するレイアウトも人気です。
人工芝と砂利の庭として整えることで、一年中緑が楽しめるうえ、ナチュラルで快適な空間づくりが可能になります。
この記事では、砂利への変更に伴うメリット・デメリットを整理し、DIYで進める場合の手順や道具選び、そして境界部分の処理方法まで、初めての方でもわかりやすくご紹介します。
見た目だけでなく、費用や使い勝手も考慮した、後悔しない庭リフォームの参考にしてください。
本記事では、以下のポイントを中心に詳しくご紹介します。
この記事を読むポイント
- 芝生から砂利に変える際のメリットとデメリットがわかる
- DIYで砂利庭にするための手順や必要な道具が理解できる
- 境界や防草シートなど仕上げに必要な工夫が学べる
- 費用相場や砂利の種類による印象の違いが把握できる
-

-
庭の芝生をやめたい人必見|手入れ不要に変える7つの方法|庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 芝生のある庭に憧れて張ってみたものの、 「手入れが大変」「放置するとすぐに荒れる」「管理の負担が大きい」 このように感じている方は少なくありません。 この記事に ...
続きを見る
庭を芝生から砂利に変える理由と基本手順

庭の手入れに時間や労力がかかりすぎると感じている方にとって、芝生から砂利への変更は非常に現実的な選択肢となります。
芝生の美しい緑は魅力的ですが、その美しさを維持するためには定期的な芝刈り、水やり、雑草取りなどの細かな手入れが必要です。
こうした作業に追われる生活から解放されたいと考える人にとって、砂利はメンテナンスの手間を大幅に軽減してくれる素材として注目されています。
砂利は雑草対策や防犯効果の面でも有効です。
防草シートと併用することで、雑草の発生を最小限に抑え、長期的に美しい状態を保つことができます。
また、人が砂利の上を歩くと音が鳴るため、防犯上の抑止力としても機能します。
さらに、砂利は色や大きさ、質感にバリエーションがあり、デザイン性の面でも庭に新たな表情を与えることが可能です。
この章では、芝生から砂利へと庭を変える際に考慮すべき理由について掘り下げ、作業全体の流れをわかりやすく解説していきます。
芝生の撤去、防草シートの設置、そして砂利敷きまでの工程を順を追って紹介することで、初めての方でも全体像がイメージしやすくなるはずです。
庭の維持管理をもっとシンプルに、かつおしゃれに変えたい方にとって、第一歩となる内容をお届けします。
- 芝生から砂利に変えるメリット・デメリット
- DIYで庭を砂利にする場合の流れと注意点
- 砂利に変える際に必要な道具と資材とは
- 芝生から砂利に変える場合の費用相場
芝生から砂利に変えるメリット・デメリット
芝生を砂利に変えることは、庭の手入れや使い勝手を大きく変える選択肢の一つです。
見た目の印象だけでなく、管理の手間や費用、防犯性にも影響するため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
ここでは、砂利のメリットとデメリットに分けて詳しく解説します。
メリット
まず大きな利点として挙げられるのが、日常のメンテナンス負担が軽減されることです。
芝生の場合、成長期には週に一度の芝刈りが必要になることもあり、水やりや雑草の除去など、維持管理に時間がかかります。
砂利であれば、こうした定期的な手入れがほとんど不要になるため、忙しい家庭にも適しています。
また、防草シートを併用することで、雑草の発生を大幅に抑えることが可能です。
これは庭の景観を保つだけでなく、除草にかかる手間やコストの削減にもつながります。
とくに広い庭では、防草効果の高さが大きな利点になります。
もうひとつ注目されているのが、防犯効果です。
砂利の上を人が歩くと音が鳴るため、不審者の侵入にすぐ気づけるという安心感があります。
これは特に住宅密集地や、夜間に周囲の目が届きにくいエリアに住んでいる方にとって、有効な防犯対策の一つとなります。
デザイン面でも砂利は優秀です。
白、グレー、ピンク、黒など多彩な色合いから選べ、和風にも洋風にも調和する素材です。
明るめの色を選べば庭全体が華やかな印象に変わり、石材や植物と組み合わせて立体的な庭づくりも楽しめます。
デメリット
一方で、砂利ならではの不便さも無視できません。
まず最もよく挙げられるのが「歩きにくさ」です。
砂利は不安定な足元になりやすく、小さなお子様や高齢者がいる家庭では転倒リスクが懸念されます。
また、ベビーカーや車椅子といった車輪付きの道具がスムーズに通れない点も、生活動線に影響を及ぼす可能性があります。
次に、完全な防草は難しいという点です。
防草シートを敷いても、耐久性が低い製品では破れたり劣化したりして、すき間から雑草が生えてくることがあります。
とくに長期的な使用を考える場合には、シート選びの質が仕上がりに直結します。
さらに、清掃の難しさもネックです。
落ち葉やゴミが砂利のすき間に入り込むと、掃き掃除だけでは取りきれず、手間がかかります。
植栽が多い家庭では、秋から冬にかけて落ち葉の片付けが大変になることもあります。
加えて、一度砂利を敷いてしまうと「元に戻すのが大変」という問題もあります。
将来的に庭の用途を変えたくなった場合、砂利の撤去や処分には手間と費用がかかります。
そのため、短期間の用途変更を前提とした施工には不向きかもしれません。
このように、砂利には手入れが簡単という大きな魅力がある一方で、使い方や環境によっては不便さを感じる場面もあります。
庭の利用目的や家族構成に応じて、芝生のままにするか砂利に変更するかを慎重に判断することが大切です。
ポイント
メリット
- 芝刈りや水やりなどの手間が不要になる
- 防草シートを併用すれば雑草の発生を抑えられる
- 歩くと音が鳴る砂利は防犯対策にも有効
- カラーバリエーションが豊富でデザインの自由度が高い
デメリット
- 砂利の上は歩きにくく、転倒リスクがある
- 完全な防草は難しく、雑草が生える可能性がある
- ゴミや落ち葉が砂利の間に入り掃除しづらい
- 砂利を撤去するには手間と費用がかかる
DIYで庭を砂利にする場合の流れと注意点
DIYで芝生の庭を砂利に変える場合、見た目よりも工程が多く、思いのほか労力がかかる作業です。
特に初めての方にとっては、手順を正確に把握し、事前準備を怠らないことが成功の鍵となります。
以下では、作業の流れを3つのステップに分けて解説し、それぞれの注意点も併せて紹介します。
芝生の撤去
最初に行うのが、既存の芝生をきれいに取り除く作業です。これを怠ると、後から芝が再び伸びてきてしまう恐れがあります。
作業内容:
- スコップや剣先スコップを使って、芝生を根ごと剥がす
- 表面だけでなく、根の深さまでしっかりと掘る
- 除草剤を事前に使って芝を枯らしておくと作業がしやすい
注意点:
- 作業量が多く体力を消耗するため、複数日に分けて作業するのも一案です
- 撤去した芝は土が付着しているため、可燃ごみとして出せない自治体もあります
- 事前に地元の廃棄ルールを確認しておきましょう
防草シートの設置
芝を剥がしたら、次は雑草対策として防草シートを敷きます。この工程が、後々のメンテナンス性を大きく左右します。
作業内容:
- 地面を平らに均し、凹凸をなくしてからシートを敷く
- シートは10cm程度重ねて敷くことで隙間からの雑草発生を防ぐ
- 専用のU字ピンや押さえ釘で、風に飛ばされないようしっかりと固定する
注意点:
- 安価なシートは紫外線や踏み圧で劣化しやすく、1年ほどで破れることもあります
- 厚手で耐久性の高い製品を選ぶことが重要です
- 施工中に穴や破れができた場合は、上から補修シートを重ねておくと安心です
砂利を敷く
最後の仕上げとして、庭全体に砂利を均等に敷き詰めます。適切な厚さと整地の丁寧さが、美観と機能性の両立につながります。
作業内容:
- 庭の面積に応じて必要な砂利の量を事前に計算し、準備しておく
- 一般的には、5cm程度の厚さを確保するのが理想
- 敷いた後はトンボなどで表面を均し、高さを揃えて整える
注意点:
- 砂利が薄すぎると、防草シートが見えてしまう場合があります
- 踏みしめる用途が多い場所では、やや厚めに敷いておくと安定性が向上します
- 配送費を抑えるため、地域のホームセンターや建材店で購入するのも一つの方法です
このように、DIYで庭を砂利に変えるためには、計画的に工程を進めることが大切です。
費用を抑えられるという利点はありますが、芝の撤去や重い資材の運搬など、体力と時間が必要になることも理解しておきましょう。
とくに広い庭や勾配のある土地では、作業が想定以上に大変になることがあります。
場合によっては、一部の工程だけでも専門業者に依頼することで、負担を軽減するという方法も検討の余地があります。
適切な準備と無理のない計画があれば、DIYでも充分に満足できる庭に仕上げることが可能です。
ポイント
- 作業は「芝生の撤去→防草シート設置→砂利敷き」の3段階
- 芝は根ごとスコップで取り除くことが重要
- 防草シートは10cm重ねてピンでしっかり固定する
- 砂利は5cm程度の厚みで均等に敷き詰める
- 芝の処分は自治体によってルールが異なるため要確認
- 安価な防草シートは劣化しやすいので耐久性重視で選ぶ
砂利に変える際に必要な道具と資材とは
芝生を撤去して砂利に変えるには、いくつかの専用道具や資材が必要になります。
作業の効率を高め、見た目の美しい庭に仕上げるためには、適切な道具選びが重要です。
ここでは、DIYで砂利敷きを行う際に準備しておきたい基本のアイテムを紹介します。
基本のアイテムは以下の通りです。
- シャベル
- 剣先スコップ
- 平鍬(てんぐわ)
- レーキ(熊手)
- 防草シート
- シート用ピン
- 一輪車
- バケツ
詳しく解説します。
まず必須となるのが、芝生を剥がすための道具です。
芝は地面にしっかり根を張っているため、シャベルや剣先スコップがあると便利です。
スコップは先の尖ったものを選ぶことで、芝の根に切り込みを入れやすくなります。
また、土を均す作業に備えて、平鍬やレーキ(熊手)も用意しておくと、仕上がりが整いやすくなります。
次に、防草対策に必要な資材として防草シートがあります。
このシートは土壌に直接光が当たるのを防ぎ、雑草の発生を抑える役割を担います。
ホームセンターなどで安価な製品も手に入りますが、耐久性の高いものを選ぶことを強くおすすめします。
防草シートの品質が悪いと、短期間で破れ、雑草が再び生えてしまうリスクがあるためです。
さらに、防草シートを固定するためのシート用ピンも欠かせません。
風などでシートがずれないよう、等間隔でしっかりと地面に打ち込む必要があります。
地面が硬い場所には、スチール製のしっかりしたピンを選ぶと施工がスムーズです。
砂利を敷く段階では、一輪車やバケツなどがあると砂利の運搬が効率的になります。
広い面積を施工する場合は特に、一度に運べる量を増やすことで作業時間の短縮が期待できます。
また、厚さを均一に整えるためのレーキや木製の板を用意しておくと、見た目の美しい仕上がりになります。
加えて、砂利自体にも注意が必要です。
使用する砂利は5cm前後の厚みで敷くことが推奨されており、庭の広さによって必要な量が変わります。
種類も豊富で、白玉砂利、グレーの砕石、ピンク系の砂利などデザインに応じて選ぶことができます。
防犯対策を意識する場合には「防犯砂利」と呼ばれる音の出るタイプも選択肢に入ります。
このように、芝生から砂利への変更には多くの道具と資材が必要ですが、それぞれの役割を理解して丁寧に準備することで、仕上がりの品質が大きく変わります。
手間を惜しまず、適切なアイテムを揃えることが、長く快適に保てる庭づくりの第一歩になります。
ポイント
- シャベル、剣先スコップ、平鍬、レーキなどが必要
- 防草シートは耐久性と透水性に優れたものを選ぶ
- シート用ピンで風飛びやズレを防ぐ
- 一輪車やバケツがあると砂利の運搬が楽になる
- 砂利は用途に合わせて色や粒の大きさを選ぶ
芝生から砂利に変える場合の費用相場
芝生を撤去し、砂利へと庭をリフォームする際にかかる費用は、庭の広さや選ぶ材料、作業の依頼方法によって大きく変動します。
ここでは、おおまかな費用感と、コストを左右する要素について解説します。
まず、プロに依頼した場合の相場は、1平米あたり約3,000円〜6,000円程度が目安となります。
この金額には、芝生の剥ぎ取り、残土の処分、防草シートの施工、砂利敷きまでの一連の作業が含まれるのが一般的です。
例えば、10平米の庭であれば、約3万円〜6万円前後が相場となるでしょう。
ただし、使用する砂利の種類や地域によって価格が変動するため、事前の見積もり確認は必須です。
また、DIYで行う場合は、費用を抑えられる一方で、道具の準備や労力が必要になります。
DIYの費用はプロの施工費用の半額程度に収まることが多いです。
具体的には、防草シートが1平米あたり200円〜500円程度、砂利が1平米分(5cm厚)で約1,000円〜2,000円程度となります。
そこにシートピンや道具代などが加わります。
たとえば、10平米をDIYで施工する場合、合計で15,000円〜30,000円ほどがひとつの目安になります。
ここで注意したいのは、「芝生の処分費用」です。
自治体によっては芝生をそのままゴミに出すことができず、専門の業者へ依頼する必要が出てきます。
この場合、別途処分費用が発生する可能性があり、想定外の出費となるケースもあります。
また、砂利の種類によっても価格は異なります。
白玉砂利や高級感のある伊勢砂利などは、一般的な砕石に比べて単価が高く、予算に応じた選定が求められます。
逆に、コストを抑えたい場合は、ホームセンターなどで手に入る砕石やリサイクル材を検討してもよいでしょう。
このように、芝生から砂利へのリフォームにかかる費用はさまざまな要素で変動します。
見た目だけでなく、機能性や将来的なメンテナンス性も踏まえて、必要な予算を検討することが大切です。
業者に依頼する場合は、複数の見積もりを比較し、内容と価格のバランスをよく確認したうえで判断するようにしましょう。
ポイント
- 業者依頼の場合:1平米あたり3,000〜6,000円が目安
- DIYの場合:半額程度の費用で抑えられる
- 芝の処分費が別途かかることがある
- 砂利の種類によって単価が大きく異なる
- ホームセンターの資材を活用すればコストダウン可能
-

-
庭を芝生以外にしたい!プロがすすめる代替素材ベスト5 | 庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 芝生は見た目に美しい一方で、芝刈りや水やり、雑草取りなど、日々のメンテナンスに手間がかかる点が課題です。 「庭の芝生をやめたい…」と感じている方にとって、芝生の ...
続きを見る
庭を芝生から砂利に変える際に知っておくこと

見た目の変化だけでなく、維持費や手間の違いといった実用面でも、芝生から砂利への変更は庭づくりにおいて大きな転機となるポイントです。
しかし、見栄えやコストだけで判断してしまうと、後になって後悔するケースも少なくありません。
実際に施工に取りかかる前に、素材の性質や手入れの頻度、防草対策の重要性などを理解しておくことが、満足のいく仕上がりへの近道となります。
例えば、砂利を敷くだけで雑草が生えなくなると思っている方も多いですが、適切な防草シートの選定と施工がなければ、その効果は長続きしません。
また、砂利の種類によっても防犯性や景観、歩きやすさなどが変わるため、目的に応じた素材選びが重要になります。
さらに、施工後の掃除のしやすさや将来的な変更のしやすさといった視点も、事前に検討しておくべき要素です。
この章では、庭を芝生から砂利に変える際に見落とされがちな注意点や、素材選びで後悔しないためのポイントを整理して紹介します。
すぐに工事に取りかかるのではなく、しっかりと準備と理解を深めておくことで、完成後の満足度が大きく変わります。
庭を快適で長く愛せる空間に変えていくために、まず知っておくべき基礎知識を確認していきましょう。
- 防草シートの役割と選び方のポイント
- 芝生と砂利の境界をきれいに仕上げる方法
- 人工芝と砂利の庭を美しく整えるコツ
- タイルと砂利で庭を魅せるデザイン例
- 砂利の種類と選び方で庭の印象が変わる
- DIYと業者依頼、費用と手間の違いを比較
防草シートの役割と選び方のポイント
防草シートは、庭に砂利を敷く際に欠かせない重要な資材です。
主な役割は、地面に光が届かないようにして雑草の成長を抑えることです。
光合成を妨げることで、種子や根から新たに生えてくる草をブロックし、美しい庭の景観を長期間保つために効果を発揮します。
多くの場合、防草シートは砂利の下に敷かれ、土壌と砂利を隔てる層となります。
この層があることで、雑草だけでなく、砂利が地面に沈み込むのを防ぐ効果もあります。
また、長期的に見たときのメンテナンスコストを抑える点でも非常に有用です。
庭を整えた直後はきれいでも、数カ月後に雑草が生えてしまうと手間と時間がかかります。
その点、防草シートは地味ながらも、庭全体の品質を左右する影の主役と言える存在です。
選び方のポイントとしては、まず「耐久性」に注目することが挙げられます。
安価なシートは数年で破れたり裂けたりすることがあり、その結果雑草が隙間から生えてきてしまうこともあります。
住宅周りの外構など、人が歩く場所や頻繁に利用する庭には、厚手で強度の高い製品を選ぶと安心です。
次に、シートの「透水性」も重要です。
透水性がないと、雨水がシートの上にたまり、水はけが悪くなってぬかるみが生じることがあります。
透水性の高い防草シートを選べば、雨水は地中に自然に染み込み、植物の根腐れや砂利の浮き上がりを防ぎやすくなります。
さらに、サイズの合ったものを選ぶことも忘れてはなりません。
敷き詰める範囲より少し広めに用意し、シート同士は10〜15cmほど重ねて敷くことで隙間を作らず、より効果的な防草効果が期待できます。
ピンやU字釘でしっかりと固定することも、長持ちさせるためには必要な工程です。
このように、防草シートは庭づくりにおける土台とも言える存在です。
見た目には現れにくい部分ですが、後々のトラブルを防ぐためにも、適切な製品選びと丁寧な施工が求められます。
ポイント
- 雑草の光合成を妨げて発生を抑えるのが主な役割
- 地面の沈下や砂利の沈み込みも防ぐ
- 耐久性の高い厚手タイプを選ぶと長持ちする
- 透水性があるシートは雨水の排水性に優れる
- シートは少し広めにカットして重ねて敷くのが効果的
芝生と砂利の境界をきれいに仕上げる方法
芝生と砂利の境界部分は、見た目の印象を大きく左右する場所です。
中途半端に仕上げてしまうと、芝の根が砂利側に伸びてしまったり、砂利が芝生に流れ込んだりといった問題が起きやすくなります。
そのため、境界を美しく、かつ実用的に保つためには、しっかりとした仕切りを設けることが重要です。
仕切り材にはいくつかの選択肢がありますが、代表的なものにレンガやピンコロ石、樹脂製のエッジ材があります。
これらを使うことで、芝と砂利のエリアを物理的に分けることができ、それぞれの素材が混ざり合うのを防ぎます。
例えば、レンガを並べるとナチュラルな印象になり、洋風ガーデンにもよく合います。
一方で、樹脂製のエッジ材は曲線が作りやすく、柔軟なデザインに対応できるのが特徴です。
仕切りを設置する際は、地面にしっかりと固定することが大切です。
表面だけに仕切りを置いただけでは、時間が経つと素材が動いてしまうため、深さ5〜10cm程度まで埋め込むと安定感が増します。
仕切り材の高さも調整し、芝の刈り込みがしやすいようにすることで、日々のメンテナンスもしやすくなります。
また、境界部分の処理によっては防草効果にも影響を与えます。
芝生が防草シートを突き破って成長するケースもあるため、芝と砂利の接する部分にはシートを二重にする、もしくは厚めの素材を使うなどの工夫も有効です。
仕切り材を設けることで、こうした境界トラブルを未然に防ぐことができます。
デザイン面でも、境界がはっきりしていると庭全体が引き締まった印象になります。
芝と砂利の色のコントラストを活かすことで、視覚的にもメリハリのある空間が作れるでしょう。
見た目と機能を両立させるためにも、境界部分の処理には時間をかけて丁寧に取り組む価値があります。
ポイント
- 境界部分にはレンガやエッジ材を設置して区切る
- 素材が混ざるのを防ぎ、見た目も整う
- 仕切り材は5〜10cm埋めて固定することで安定感アップ
- 境界部の防草対策も二重にするなど工夫が必要
- 境界が明確だと庭全体が引き締まった印象になる
人工芝と砂利の庭を美しく整えるコツ
人工芝と砂利を組み合わせた庭づくりは、見た目の美しさとメンテナンスの手軽さを両立できる点で人気があります。
異なる素材を使うことで空間にメリハリが生まれ、視覚的にも楽しめるデザインが可能になります。
ただし、整然とした仕上がりにするためには、いくつかの工夫が必要です。
まず大切なのは、素材の質感と色の相性です。
人工芝には濃淡の違いや毛足の長さが異なる製品があります。
高品質なものを選ぶと、天然芝に近い見た目と触り心地を再現でき、庭全体の質感を高めることができます。
一方で、砂利は明るめの白やグレー系を選ぶと人工芝とのコントラストがはっきりし、境界線が際立ちます。
砂利の粒が細かすぎると人工芝に入り込んでしまうため、粒が大きめで丸みのあるタイプを選ぶと、清掃もしやすくなります。
施工時には、人工芝と砂利の境目に仕切り材を設けることが重要です。
これにより、素材同士が混ざるのを防ぎ、美しいラインを維持することができます。
樹脂エッジやレンガを使うことで、仕切りながらデザイン性を高めることも可能です。
特に人工芝は端がめくれやすいため、ピンでしっかり固定し、境界部分も接着剤や専用テープで補強しておくと安心です。
また、配置バランスも見た目に大きく影響します。
例えば、リビングから見える位置に人工芝エリアを配置し、その周囲を砂利で囲むことで、視線が集まりやすい中心部分をグリーンにすることができます。
逆に、歩行用の通路には砂利を敷いておくと踏み固めにも強く、機能的な動線が生まれます。
人工芝と砂利を組み合わせることで、年間を通じて青々とした庭の景観を維持しながら、手入れの手間も抑えることが可能です。
ただし、施工の精度が美観に直結するため、見た目にこだわる場合は丁寧な下準備と素材選びが欠かせません。
配置とバランスを意識することで、洗練された庭空間を演出することができます。
ポイント
- 質感と色の相性を意識して素材を選ぶ
- 境界に仕切り材を使って混ざりを防ぐ
- 人工芝の端はピンや接着剤でしっかり固定する
- リビング前などの視線が集まる場所に人工芝を配置するのが効果的
- 清掃のしやすさも考慮して砂利の粒を選ぶ
タイルと砂利で庭を魅せるデザイン例
タイルと砂利を組み合わせた庭は、シンプルながらもスタイリッシュな印象を演出できます。
この素材の組み合わせは、色彩や質感のコントラストによって空間にリズムを与えるため、視覚的な美しさと実用性の両立が可能です。
特に洋風・モダンな外構を目指す家庭にとっては、非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。
デザインの基本は、タイルを「動線」として配置し、その周囲を砂利で囲むパターンです。
たとえば、玄関から庭への通路に大判の平板タイルを敷き、両脇に白やグレーの砂利を敷くことで、自然と歩行ルートが導かれます。
直線だけでなく曲線やランダム配置にすることで、ナチュラルさや遊び心も加わります。
さらに、植栽をタイルと砂利の境界に加えることで、庭全体がより立体的に見えるようになります。
タイルには多様な色や質感があり、滑りにくい加工が施されたエクステリア用の製品を選ぶと安全性も確保できます。
一方、砂利の色をタイルと同系色にすれば統一感が生まれ、あえて対照的な色にすると印象に残るアクセントになります。
こうした色彩の工夫によって、日常の庭がまるでデザイン性の高いガーデンカフェのような雰囲気に変わることもあります。
注意点としては、タイルと砂利の接地面に段差ができないように調整することが大切です。
段差があると見た目が不自然になるだけでなく、つまずきやすくなるため、安全性にも配慮しましょう。
下地をしっかり整え、タイルと砂利の高さを均一に仕上げることが美しい庭づくりには欠かせません。
このように、タイルと砂利を使った庭のデザインは自由度が高く、自分らしい空間演出が楽しめます。
どちらの素材もメンテナンスが比較的簡単で、長期間にわたり美観を維持しやすい点も嬉しいポイントです。
ポイント
- タイルで動線を作り、周囲に砂利を敷くデザインが人気
- 色や質感のコントラストが庭の印象を変える
- タイルには滑りにくいエクステリア用製品を選ぶと安全
- タイルと砂利の高さをそろえてつまずきを防止
- デザインの自由度が高く、自分らしい庭を演出できる
-

-
庭を芝生からタイルで快適!初心者向けの手順と注意点7つ | 庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 「庭の芝生をタイルに変えたい…」 上記のような悩みを抱える人の多くは、芝生の管理に疲れ、もっと手入れの少ない庭づくりを検討しているのではないでしょうか。見た目の ...
続きを見る
砂利の種類と選び方で庭の印象が変わる
砂利は、見た目だけでなく機能性にも影響を与える重要な素材です。
選ぶ砂利の種類によって、庭全体の雰囲気や印象が大きく変化するため、目的や好みに応じた選び方をすることがポイントになります。
一般的に使用される砂利には、砕石、化粧砂利、玉砂利、防犯砂利などがあります。
それぞれに特徴があり、用途に応じて使い分けることが推奨されます。
例えば、ナチュラルで落ち着いた印象に仕上げたい場合は、丸みを帯びた玉砂利が向いています。
淡い色の玉砂利を選ぶことで、やさしく柔らかな雰囲気を作ることができます。
一方で、シャープな印象や現代的なデザインを求める場合には、砕石タイプが適しています。
角ばった形状で無機質な雰囲気があるため、モノトーンの外構やモダンな住宅によくなじみます。
踏み締めにも強く、通路などの実用性を求める場所にも使いやすい素材です。
防犯対策として人気があるのが防犯砂利です。
歩くたびにジャリジャリと音が鳴るよう加工されており、侵入者の存在に気づきやすくなります。
砂利としての機能に加えて、防犯効果を期待する場合に選ぶとよいでしょう。
色の選び方にも工夫が必要です。
たとえば、建物の外壁やフェンスの色と調和させることで、庭全体に統一感を持たせることができます。
逆に、あえてコントラストを強調した色味を取り入れることで、印象的なアクセントを加えることも可能です。
また、砂利の大きさにも注意が必要です。
粒が細かすぎると風で飛ばされたり、歩行時に靴の裏にくっついて屋内に持ち込まれることがあります。
粒の大きさは用途に合わせて選び、歩行が多い場所には中粒〜大粒を使用するのが一般的です。
このように、砂利は種類・形状・色・サイズの選び方によって、庭の雰囲気や使い勝手に直結します。
単に敷くだけの素材と思われがちですが、しっかりと計画を立てて選ぶことで、見た目も機能も満足のいく庭に仕上がります。
ポイント
- 丸い玉砂利は柔らかくナチュラルな雰囲気に
- 砕石はシャープでモダンな印象に仕上がる
- 防犯砂利は歩行音が大きく防犯効果がある
- 色や粒の大きさによって庭の印象が変わる
- 使用目的に応じた砂利を選ぶことが重要
DIYと業者依頼、費用と手間の違いを比較
芝生から砂利へと庭を変える方法には、DIYで自分自身で行う方法と、専門の業者に依頼する方法の2つがあります。
それぞれにメリットとデメリットがあり、費用や作業の負担、仕上がりの質などに明確な違いがあります。
DIYの最大の魅力は、費用を大きく抑えられることです。
材料費だけで済むため、業者に依頼する場合の半分程度のコストで済むこともあります。
また、自分のペースで作業ができるため、空いた時間を活用して少しずつ進められるのも利点です。
自らの手で庭づくりを行う達成感を味わえるというのも、DIYならではの魅力といえるでしょう。
一方で、DIYには時間と体力が必要です。
特に芝生の撤去作業や土の整地、防草シートの設置といった作業は、見た目以上に重労働になります。
また、初めての方が行う場合は、砂利の厚みや均し方にムラが出るなど、仕上がりに不満が残るケースもあります。
必要な道具を揃える手間や、処分物の対応といった面倒も発生します。
業者に依頼した場合は、仕上がりの美しさや耐久性に優れるのが大きなメリットです。
プロは長年の経験から最適な施工手順を熟知しており、効率よく作業を進めることができます。
土壌の状況に合わせた処理や、排水を考慮した施工も任せられるため、長期的に見て安心感があります。
ただし、業者に頼む場合は施工費が発生します。
相場としては、1平米あたり3,000円〜6,000円前後が一般的で、庭全体を整えると数万円〜十数万円になることも珍しくありません。
また、依頼する業者によってはサービス内容や金額に差があるため、複数社からの見積もりを比較することが重要です。
どちらの方法を選ぶにせよ、庭の広さや自分の体力、時間的余裕、仕上がりへのこだわりなどを総合的に考慮して判断することが大切です。
部分的にDIYし、一部の作業のみ業者に任せるというハイブリッドな方法も選択肢として有効です。
自分にとって最適な方法を見極めて、後悔のない庭づくりを進めましょう。
ポイント
- DIYは費用が抑えられるが時間と労力が必要
- 業者は仕上がりが安定し、耐久性が高い
- 両者のメリットを活かしたハイブリッドも有効
【まとめ】庭を芝生から砂利に変えるときに押さえておきたいポイント

庭を芝生から砂利に変えるという選択は、見た目の変化だけでなく、日々の手入れや費用面、防犯性など、さまざまな側面に影響を与えます。
DIYで進める場合でも業者に依頼する場合でも、事前に知っておくべき基礎知識や注意点を理解しておくことが、美しく快適な庭づくりへの第一歩となります。
ここでは、これまで紹介した内容を総合的に整理し、実践前に確認しておきたいポイントをまとめました。
この記事のまとめ
- 芝生より砂利は手入れの手間が少なくメンテナンスが楽
- 防草シートを使うことで雑草対策の効果が大きく向上
- 砂利の上を歩く音が防犯効果を高める
- 白やピンクなどの砂利は庭を明るく見せるのに効果的
- 砂利はベビーカーや車椅子では走行しづらい場合がある
- 落ち葉の掃除は芝生より砂利の方が手間がかかる
- 芝生の撤去作業は想像以上に体力が必要
- DIYでは砂利の厚みを均一に保つことが美観の鍵
- 防草シートは耐久性と透水性の高い製品を選ぶことが重要
- 境界に仕切りを設けることで芝と砂利の混ざりを防げる
- 人工芝と砂利の組み合わせはデザイン性と実用性の両立が可能
- タイルと砂利の組み合わせは洋風・モダンな庭に最適
- 砂利の種類・色・粒の大きさによって庭の印象が大きく変わる
- DIYと業者施工では費用と労力に大きな差がある
- 芝の処分や資材の運搬も含めて事前に全体計画を立てることが大切
庭を芝生から砂利に変えることで、暮らし方や庭の見え方が一変します。
ライフスタイルや目的に合わせて適切な方法を選べば、長く快適に使える庭づくりが実現できます。
慎重に計画を立てて、自分らしい庭を整えていきましょう。
芝生から砂利に変える前に知っておきたい10の注意点
- 芝生の撤去は想像以上に重労働
- 芝の廃棄は地域ルールの確認が必須
- 防草シートは安価なものだとすぐ劣化
- 透水性のある防草シートを選ぶべき
- 砂利は適切な厚みで敷く必要がある
- 落ち葉やゴミの掃除が意外と大変
- 車椅子やベビーカーでは通りにくくなる
- 芝と砂利の境界は明確に仕切ること
- DIYは道具の準備と手間が多い
- 一度砂利を敷くと戻すのは大変
-

-
庭の芝生をやめたい人必見|手入れ不要に変える7つの方法|庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 芝生のある庭に憧れて張ってみたものの、 「手入れが大変」「放置するとすぐに荒れる」「管理の負担が大きい」 このように感じている方は少なくありません。 この記事に ...
続きを見る
-

-
庭を芝生からタイルで快適!初心者向けの手順と注意点7つ | 庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 「庭の芝生をタイルに変えたい…」 上記のような悩みを抱える人の多くは、芝生の管理に疲れ、もっと手入れの少ない庭づくりを検討しているのではないでしょうか。見た目の ...
続きを見る
-

-
庭を芝生以外にしたい!プロがすすめる代替素材ベスト5 | 庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 芝生は見た目に美しい一方で、芝刈りや水やり、雑草取りなど、日々のメンテナンスに手間がかかる点が課題です。 「庭の芝生をやめたい…」と感じている方にとって、芝生の ...
続きを見る
芝生から砂利に変えたい際にあるよくある質問(FAQ)
-
砂利に変えたあと、本当に「雑草取りほぼゼロ」になりますか?
-
「ゼロ」ではありませんが、防草シート+十分な厚みの砂利(目安5cm以上) ができていれば、草むしりの頻度はかなり減ります。
ただし…- シートの継ぎ目や端部分
- シートを固定したピンの周り
- 風で運ばれてきた土がたまったところ
このあたりからは、どうしてもポツポツと雑草が出ます。
年に何度か、「見つけたらその場で抜く」くらいの軽い手入れは必要、というイメージを持っておくとギャップが少ないです。
-
子どもや高齢の家族がいるけど、砂利にしたら危なくないですか?
-
砂利はどうしても足元が不安定なので、
- よく歩く場所 → タイル・平板・コンクリートで通路を作る
- その周り → 砂利にする
という「砂利オンリーにしない設計」が安心です。
特に以下に注意すると安全性が上がります。- 粒が尖った砕石よりも、角が丸い砂利を選ぶ
- 玄関前やステップの周りは、フラットなタイルやコンクリ仕上げにする
- 段差を作らず、つまづきポイントを減らす
「庭の全部を砂利にする」のではなく、
“歩くところは歩きやすく、飾るところは砂利で” と分けて考えると失敗しにくいです。
-
DIYと業者、結局どっちがいいの?判断の目安が知りたいです。
-
ざっくり判断基準はこんな感じです。
DIY向き
- 庭の面積が〜10㎡前後とそこまで広くない
- 休日にコツコツ作業するのが好き
- 軽トラや一輪車が使える(砂利を運べる)
- 多少のムラは気にしない
業者向き
- 庭が広い(15〜20㎡以上)
- 土が固かったり、段差・勾配が大きい
- 腰痛持ち・体力に不安がある
- 将来のひび割れや水はけなども含めてプロに任せたい
中間案として、
- 「芝の撤去と処分だけ業者、砂利敷きは自分」
- 「防草シートまで業者、砂利だけDIY」
という分担もアリです。費用と体力を両方バランスよく抑えられます。
-
落ち葉が多い庭なんですが、砂利にすると掃除が大変って本当ですか?
-
落葉樹が多い庭では、砂利は正直ちょっと大変です。
- ほうきで掃いても、砂利の間に葉が入り込む
- ブロワーで飛ばしても、砂利も一緒に飛びやすい
対策としては、
- 木の下だけは土やウッドチップ・タイル仕上げにする
- 砂利の粒を大きめ&丸めにして、掃きやすくする
- 落葉シーズンだけ、ネットを仮敷きしておいてまとめて撤去
「お庭全体を砂利」にする前に、
“落ち葉が特にたまるゾーン”は別素材にする、という選択も考えておくとラクになります。
-
砂利にしたあと、もし将来また芝生や別の素材に変えたくなったらどうなりますか?
-
記事にもある通り、砂利は「戻すのが大変」な素材です。
- 砂利を一度どかす
- 防草シートを剥がす
- 必要なら土を入れ替え・整地し直す
という工程が必要になるので、最初の芝生撤去よりも大変になることもあります。
将来の選択肢を残したいなら、
- 庭全体ではなく、一部だけ砂利ゾーンにする
- 「花壇まわりだけ砂利」「通路だけ砂利」など、部分使いから始める
といった形が安心です。
いきなり全面リフォームに踏み切らず、 “小さく試してから広げる” ことを意識すると、後悔がぐっと減ります。
