本記事はプロモーションが含まれています
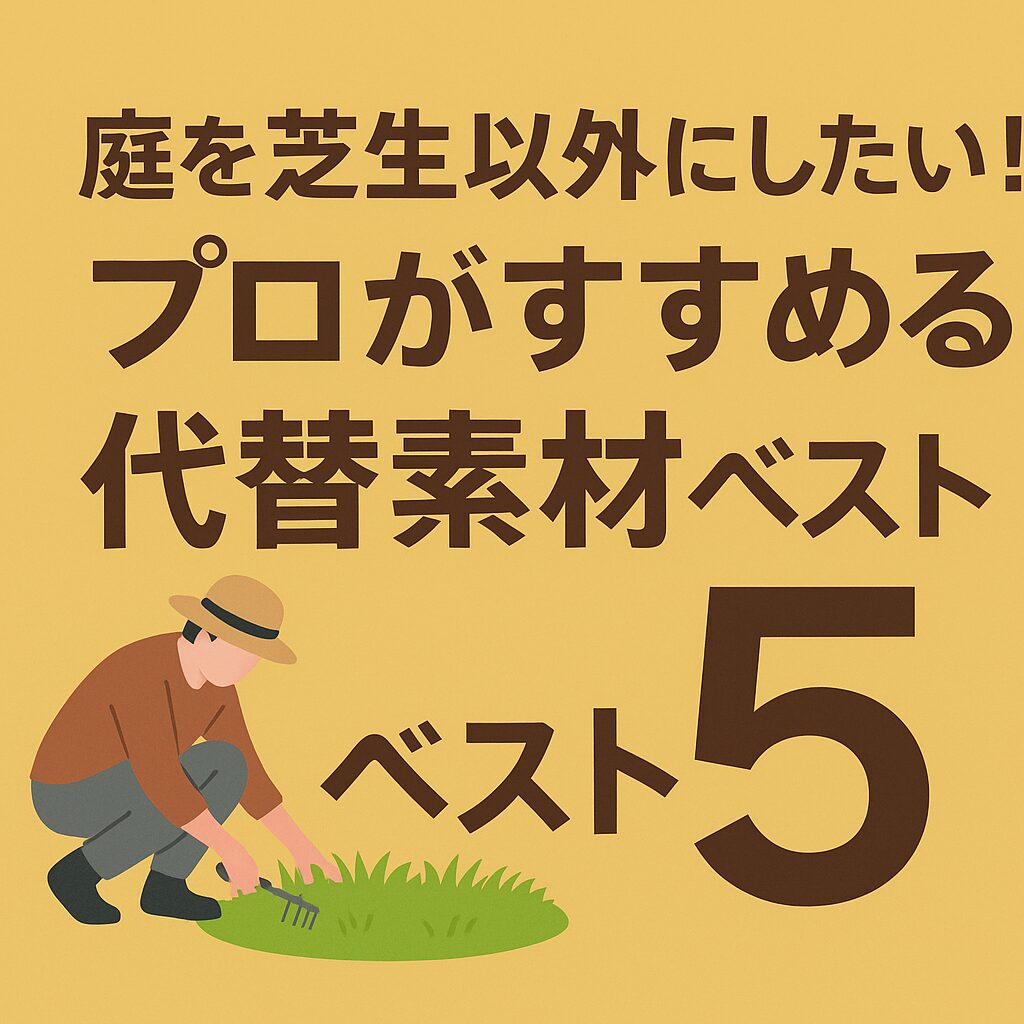
芝生は見た目に美しい一方で、芝刈りや水やり、雑草取りなど、日々のメンテナンスに手間がかかる点が課題です。
「庭の芝生をやめたい…」と感じている方にとって、芝生の代わりとなる素材や植物の選定は、快適な庭を維持するための重要なステップになります。
この記事では、芝生の代わりにおすすめのグランドカバー植物や、注目されているクラピア、乾燥に強いセダムについて詳しく解説します。
また、香りや見た目を楽しめるハーブや、管理がしやすい砂利、機能的なタイルの活用法にも触れていきます。
さらに、芝生を撤去したあとの土壌改良や、庭の芝生をやめる費用の目安、芝生を剥がしてレンガを敷く際の施工アイデアなど、導入から仕上げまでのポイントを幅広く網羅しています。
芝生以外の素材や植物を上手に取り入れることで、見た目にも機能的にも満足のいく庭をつくることができます。
自分に合った方法で、無理のない「緑」のある暮らしを叶えてみてはいかがでしょうか。
この記事を読むポイント
- 芝生の代わりに使えるグランドカバー植物の選び方
- クラピアやセダムなど芝生代替植物の特徴と注意点
- 芝生以外の素材(砂利・タイル・レンガなど)の活用方法
- 芝生をやめたあとの費用や土壌改良のポイント
庭を芝生以外で緑を楽しむ方法とは

庭に自然の緑を取り入れたいと考える方にとって、「芝生」は最もポピュラーな選択肢のひとつです。
しかし、実際に芝生を維持しようとすると、こまめな芝刈りや水やり、雑草の除去など、思いのほか手間や時間がかかるものです。
こうした管理負担を軽減しつつ、庭の美観や快適さを保ちたいと考える方も多いのではないでしょうか。
そんな「庭を芝生以外にしたい…」という悩みに対し、お応えします。
具体的には、グランドカバー植物、ハーブ、人工芝、タイル、砂利、レンガなど、さまざまな素材や植物を活用する方法があります。
それぞれに異なる特徴があり、用途や庭の環境に応じて選ぶことで、芝生に代わる魅力的な庭づくりが可能になります。
特に、日当たりの条件や人の往来の多さ、ペットやお子様の有無など、生活スタイルに合った選び方をすることが、後悔のない庭リフォームにつながります。
また、デザイン性や季節感を重視するか、メンテナンスの手軽さを優先するかによっても、選択肢は大きく変わってきます。
この章では、芝生以外で庭に緑や心地よさを取り入れるための方法について、実用的な視点からわかりやすく解説していきます。
庭づくりにおける可能性を広げる一歩として、ぜひ参考にしてみてください。
- 芝生の代わり グランドカバーの選び方
- 芝生の代わり クラピアの特徴と注意点
- 芝生の代わり セダムのメリットとは
- 芝の代わりになるハーブの種類と活用法
- 芝生をやめてタイルを敷く利点と注意点
- 芝生を剥がしてレンガを敷く施工アイデア
芝生の代わり グランドカバーの選び方
庭に緑を取り入れたいが、芝生の管理が大変だと感じる方にとって、「グランドカバー植物」は魅力的な選択肢です。
グランドカバーとは、地面を覆うように広がって育つ植物の総称で、雑草の抑制や見た目の美しさを保つために使われます。
しかし、種類が非常に多いため、何を基準に選べば良いのか迷う方も少なくありません。
まず注目すべきポイントは、「日照条件」と「踏み圧への強さ」です。
日当たりの良い庭には明るい光を好む植物、例えばタイムやリッピア(ヒメイワダレソウ)などが適しています。
一方、日陰や半日陰の場所であれば、ツルニチニチソウやアイビーなどが活躍します。
また、小さな子どもやペットが頻繁に通る場所では、踏みつけに強い種類を選ぶ必要があります。
セダム系の多肉植物やクラピアなどは、その点で有力な候補です。
さらに、見た目の印象も重要です。
ナチュラルガーデンにしたい場合は、繁殖力のある草花を組み合わせると自然な雰囲気が出ます。
反対に、手入れの手間を最小限にしたいなら、成長スピードが遅く、背丈が低い品種を選ぶとよいでしょう。
例えば、ダイカンドラやクローバーは、見た目が芝に近く、ナチュラルかつ手間の少ない選択肢として知られています。
このように、グランドカバー植物の選定では、「庭の環境」と「管理のしやすさ」、そして「求めるデザイン」の3点を意識して比較・検討することが大切です。
あらかじめ用途や目的を明確にしておけば、自分の庭にぴったりの植物を見つけやすくなるでしょう。
ポイント
- 日照条件に応じて植物を選ぶことが重要
- 踏み圧に強い種類は子どもやペットのいる家庭向き
- 見た目のデザインに応じた植物の選定が効果的
- 管理のしやすさと庭の目的に合わせた選び方が大切
芝生の代わり クラピアの特徴と注意点
クラピアは、近年人気を集めているグランドカバープランツの一つで、「芝生の代替」として注目されています。
特に、芝刈りや水やりなどの手間を軽減したい方にとって魅力的な選択肢です。
クラピアはイワダレソウを品種改良して生まれた植物で、地面を這うように成長し、短期間で広範囲を覆う性質があります。
最大の特徴は、その「繁殖力の高さ」と「管理のしやすさ」です。
クラピアは多年草で、一度植えると長期間にわたって緑を保ちます。
さらに、病害虫にも比較的強く、雑草の侵入を抑える効果があるため、メンテナンスの回数を減らせるのもメリットです。
春から秋にかけて小さな白やピンクの花を咲かせる品種もあり、庭に彩りを添える存在としても楽しめます。
ただし、注意点もあります。
まず、クラピアは種ではなく苗で販売されるため、初期費用がやや高くつく傾向があります。
また、踏みつけにはある程度強いとはいえ、芝生ほどの耐久性はありません。
頻繁に人が歩く場所にはやや不向きで、歩道や遊び場に使う場合には敷石などとの併用が必要になることもあります。
さらに、クラピアは地中でランナーを伸ばして成長するため、植栽エリアの境界が曖昧になりやすい点にも注意が必要です。
意図しない場所に広がるのを防ぐには、根止め材やレンガなどで仕切ることが望ましいでしょう。
これらを踏まえると、クラピアは「見た目」と「手入れの簡便さ」を両立したい方に向いていますが、使い方や設置場所をよく考慮した上で導入することが成功のカギとなります。
ポイント
- 手入れが楽で、病害虫に強い多年草として人気
- 短期間で広がる繁殖力があるため、管理がしやすい
- 初期費用が高く、踏み圧にはやや弱い面がある
- 境界対策が必要で、ランナー対策に根止めが有効
芝生の代わり セダムのメリットとは
セダムは、多肉植物の一種でありながら、グランドカバーとして非常に優れた特性を持っています。
その特徴から、芝生の代わりとして取り入れる人が増えており、特に「乾燥に強く、水やりの手間を減らしたい」というニーズに応える植物です。
セダムの最大のメリットは、「極めて高い乾燥耐性」と「成長のゆるやかさ」です。
もともと過酷な環境でも生育できる性質を持っているため、真夏の水切れに悩まされることが少なく、旅行などで数日水やりを忘れても枯れにくいという安心感があります。
また、ほとんどの品種が5〜15cm程度の高さで成長が止まるため、芝刈りのような手間も不要です。
もう一つの利点は、「多彩な色や形を楽しめること」です。
セダムには、黄緑色・赤みがかった緑・銀灰色など、さまざまな葉色や質感があり、単調になりがちな庭の足元にアクセントを加えることができます。
デザイン性を重視する方や、ナチュラルガーデンを目指す方にとって、理想的な素材となるでしょう。
ただし、セダムにも弱点はあります。
主に寒冷地での冬越しに注意が必要です。品種によっては霜に弱く、地上部が枯れてしまうことがあります。
また、頻繁に人が歩く場所には不向きで、踏み圧に弱い種類が多いため、動線の確保には別素材を併用するのが賢明です。
このように、セダムは「乾燥に強く、手間がかからない植物」として芝生の代替に適していますが、設置場所や気候条件をよく見極めて活用することが大切です。
適切な場所に配置すれば、機能性と見た目を兼ね備えた魅力的なグリーンカバーになります。
ポイント
- 高い乾燥耐性があり、水やりが少なくて済む
- 成長が遅く、芝刈りの手間がかからない
- 多彩な色や形で、庭の足元にアクセントを加えられる
- 寒冷地や踏み圧には弱く、設置場所の選定が重要
芝の代わりになるハーブの種類と活用法
芝生の代替として注目されている選択肢のひとつが「ハーブのグランドカバー化」です。
特に、手入れのしやすさと香りのある癒しの空間を同時に実現したい方におすすめです。
ハーブは比較的成長が早く、香りによって虫を遠ざける効果もあるため、機能性と美観の両立が期待できます。
代表的な種類としては、「クリーピングタイム」や「ローマンカモミール」があります。
これらは地面を這うように広がり、芝のような見た目を保ちながら、ふんわりとした香りで庭の雰囲気を和らげてくれます。
特にクリーピングタイムは踏みつけに強く、通路やアプローチにも使える点が魅力です。
さらに「ミント」や「オレガノ」も選択肢に入りますが、繁殖力が非常に強いため、植える範囲をきちんと区切らないと他の植物のスペースまで侵食してしまう恐れがあります。
そのため、プランターや囲いの中に限定して使うなど、管理面での工夫が必要になります。
活用方法としては、庭全体に敷き詰めるだけでなく、タイルや石畳の間に植えることで、デザイン性の高いナチュラルガーデンを演出することも可能です。
また、料理やティーに使える品種を選べば、日常生活でも楽しみが広がります。
ただし、ハーブは品種によって耐寒性や耐暑性が異なるため、地域の気候に合った種類を選定することが大切です。
初めて導入する場合は、複数の種類を試して庭に適したものを見極めるのも良いでしょう。
ポイント
- クリーピングタイムやカモミールは踏み圧にも強い
- 香りと見た目を楽しめ、癒し効果もある
- 繁殖力が強い品種は管理に注意が必要
- タイルや石との組み合わせでナチュラルガーデンを演出
芝生をやめてタイルを敷く利点と注意点
芝生の管理が負担に感じられる場合、タイル敷きに変更することは非常に現実的な選択肢です。
メンテナンスの手間が減るだけでなく、デザイン性や機能性の向上にもつながります。とくに、モダンで清潔感のある印象を与えたいときには、タイル舗装が効果的です。
タイルの主な利点は、「雑草対策」や「泥はね防止」にあります。
芝生ではどうしても雑草の発生や雨の日のぬかるみが気になりますが、タイルを敷けばその心配がほとんどなくなります。
また、掃除もしやすく、落ち葉やゴミをさっと掃き取るだけで清潔な状態を保てます。
加えて、アウトドアリビングやバーベキュースペースとしての活用にも適しています。
家具を安定して配置できる点や、火気を扱っても燃え広がるリスクがない点は、芝生にはない大きなメリットです。
一方で、注意すべき点もあります。
まず、施工には専門的な技術が求められる場合が多く、DIYでの設置には限界があります。
下地の処理が不十分だと、雨水の排水が悪くなったり、タイルが浮いたりする原因にもなります。
また、夏場に表面温度が上がりやすい素材もあるため、使用目的や場所に応じて選ぶことが重要です。
見た目を損なわず、快適さを維持するには、素材選びと配置のバランスがカギになります。
たとえば、タイルだけで全面を覆うのではなく、一部に植栽スペースや砂利を組み合わせることで、機能性と自然な雰囲気の両立が可能です。
ポイント
- 雑草対策と泥はね防止に優れ、掃除もしやすい
- デザイン性が高く、アウトドア空間に最適
- 下地処理が難しく、DIYには不向きな面がある
- 素材によっては夏に熱を持ちやすくなる
-

-
庭を芝生からタイルで快適!初心者向けの手順と注意点7つ | 庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 「庭の芝生をタイルに変えたい…」 上記のような悩みを抱える人の多くは、芝生の管理に疲れ、もっと手入れの少ない庭づくりを検討しているのではないでしょうか。見た目の ...
続きを見る
芝生を剥がしてレンガを敷く施工アイデア
芝生を撤去したあとの庭のデザインとして、「レンガ敷き」は温かみのあるナチュラルな仕上がりが魅力です。
特に洋風の外構やカントリーテイストの庭を目指している方にとっては、レンガはぴったりの素材と言えるでしょう。
レンガの施工にはいくつかの方法がありますが、代表的なのは「砂利敷き+並べる」簡易施工と、「モルタル固定」による本格的な方法です。
前者はDIYにも向いており、必要な工具が揃えば個人でも対応可能です。
レンガの間に砂や芝目土を詰めて固定することで、適度な通気性と水はけを確保できます。
デザイン面では、「ヘリンボーン」や「市松模様」などの敷き方によって、印象が大きく変わります。
遊び心を加えるために、異なる色味のレンガを混ぜるという工夫も面白い方法です。
また、レンガの目地にグランドカバー植物を植えると、硬い印象を和らげ、季節ごとの変化も楽しめます。
ただし、注意点もいくつかあります。
まず、レンガは素材によっては水を吸いやすく、凍結による劣化が生じることがあります。
寒冷地では耐凍害性能のある製品を選ぶことが大切です。
また、設置面が水平でないと、雨水がたまりやすくなったり、レンガが沈んだりする可能性もあります。
そのため、下地処理をしっかり行うことが美しい仕上がりにつながります。
施工後のメンテナンスとしては、苔や黒ずみが気になる場合に備えて、定期的な清掃や防草対策を施すと良いでしょう。
こうしたひと手間が、長く快適に使える庭づくりに直結します。レンガの温かみを生かしながら、自分だけの庭空間を演出してみてはいかがでしょうか。
ポイント
- 自然な雰囲気と温かみが出せる素材
- DIYでも可能で、敷き方の工夫で個性が出せる
- 耐凍害性のあるレンガを選ぶ必要がある
- 水はけを確保する下地処理が美観維持に重要
-

-
庭の芝生をやめたい人必見|手入れ不要に変える7つの方法|庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 芝生のある庭に憧れて張ってみたものの、 「手入れが大変」「放置するとすぐに荒れる」「管理の負担が大きい」 このように感じている方は少なくありません。 この記事に ...
続きを見る
庭 芝生以外にかかる費用と管理の工夫

芝生を手放して他の素材や植物を導入したいと考えたとき、まず気になるのが「費用」と「手入れの手間」ではないでしょうか。
せっかく芝生からの切り替えを検討しても、どれくらいの予算が必要になるのか、維持はどの程度ラクになるのかがわからなければ、不安や迷いが生じやすくなります。
芝生以外の選択肢としては、人工芝、グランドカバー植物、砂利、タイル、レンガなどがありますが、それぞれ初期費用や施工の難易度、必要なメンテナンスの頻度が異なります。
たとえば、初期費用は高くてもその後の管理がほとんど不要な素材もあれば、逆に導入コストは安く済むものの、手入れの頻度が高いものも存在します。
また、業者に依頼するかDIYで行うかによっても、総額には大きな差が出てきます。
加えて、雑草対策や排水対策など、見落としがちな追加工事の有無も予算に影響する要素です。
さらに、導入後の維持管理が難しいと、結果的に手間やコストが増えてしまうこともあります。
この章では、庭に芝生以外の素材や植物を取り入れる際にかかる費用の目安と、それぞれの管理に関する工夫について詳しく解説していきます。
長期的に見て満足のいく庭づくりを実現するための参考として、実用的な情報をお届けします。
- 庭の芝生をやめる 砂利を敷くメリットとは
- 庭の芝生をやめたい人向けの素材比較
- 庭の芝生をやめる 費用と施工の目安
- 芝生をやめたあとに必要な土壌改良とは
庭の芝生をやめる 砂利を敷くメリットとは
庭の芝生を維持するには、水やりや芝刈り、雑草取りなど定期的な手入れが欠かせません。
こうした管理の手間や費用が負担に感じられる方にとって、「砂利を敷く」という選択は、有効な代替手段となります。
砂利は施工後の維持管理が非常に楽で、見た目もシンプルながら洗練された印象を与える素材です。
第一に注目したいのが、雑草抑制効果です。
地面に防草シートを敷いた上に砂利を敷くことで、太陽光を遮断し、雑草が育ちにくい環境をつくることができます。
特に、雑草の繁殖が激しい時期でも草取りの手間を大幅に軽減できる点は、日々の手入れに時間をかけたくない方には大きな利点です。
さらに、排水性にも優れており、雨が降った際に水たまりができにくくなります。
芝生の場合、土壌によってはぬかるみが発生することがありますが、砂利は水をすっと地中へ逃がしてくれるため、足元が汚れる心配も少なくなります。
また、乾燥時期でもホコリが舞いにくいため、衛生的な面でもメリットがあります。
デザイン性の高さも見逃せません。
砂利には白や黒、グレー、赤茶など多彩な色味があり、住まいの外観や周囲の植栽と調和させることが可能です。
和風庭園にも洋風ガーデンにも対応でき、敷くだけで統一感のある空間が生まれます。
また、踏みしめたときの「音」が防犯対策としても効果を発揮することがあるとされています。
ただし、注意すべき点としては、砂利が敷地の外に散らばりやすいことや、踏圧によって沈みこみ、見た目が不揃いになることがあるということです。
そのため、縁取りをつけて砂利の移動を防ぐ工夫や、定期的に均す手間は考慮しておく必要があります。
このように、砂利はメンテナンスを最小限に抑えつつ、見た目も整えたい方に適した選択肢です。
芝生を手放した後の庭の活用法として、非常に実用的な素材と言えるでしょう。
ポイント
- 雑草を抑える効果が高く、防草対策として有効
- 水はけが良く、ぬかるみを防げる
- 色や素材のバリエーションが豊富でデザイン性も高い
- 踏み固めや散乱を防ぐ工夫が必要
-
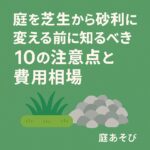
-
庭を芝生から砂利に変える前に知るべき10の注意点と費用相場|庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 庭を芝生から砂利に変えたいと考えている方の中には、 「手入れが大変」「芝生をやめるべきか迷っている」 このように感じている方も多いのではないでしょうか。 この記 ...
続きを見る
庭の芝生をやめたい人向けの素材比較
芝生をやめたいと考える背景には、管理の負担、コスト、日照条件の問題などさまざまな理由があります。
そこで、芝生に代わる素材を検討する際には、それぞれの特徴を比較しながら自分のニーズに合った選択をすることが大切です。
ここでは代表的な代替素材をいくつか紹介し、その性質や用途に応じた使い分けを解説します。
まず、「人工芝」は芝生の見た目をそのままに、手入れをほぼ不要にできる素材です。
耐久性に優れ、常緑の見た目を1年中維持できますが、製品によっては表面温度が上がりやすいという点には注意が必要です。
特に夏場は高温になるため、小さな子どもやペットのいる家庭では注意が求められます。
次に、「砂利」は先述のようにメンテナンスが簡単で、和洋問わず庭のスタイルに合わせやすいのが特徴です。
ただし、歩行時に足裏への負担がかかることがあり、長時間の移動には向いていません。
また、音が気になる方には不向きなケースもあります。
「タイル」や「レンガ」は、デザイン性と実用性を兼ね備えた素材です。
アウトドア家具やバーベキューセットを置くスペースとしても最適で、平坦な地面を保てるため移動や掃除がしやすいという利点があります。
ただし、施工費用や下地処理に関する知識が必要になるため、ある程度の初期投資を想定する必要があります。
さらに、「グランドカバー植物」も選択肢の一つです。
クラピアやセダム、タイムなど、低草丈で横に広がる性質の植物を植えることで、自然な緑を維持しつつ手入れの負担を減らすことができます。
植物を取り入れることで庭に季節感や香りを加えられるのも大きな魅力です。
ただし、完全に手入れ不要ではないため、ある程度の剪定や管理は必要になります。
このように、素材ごとに特徴や適性が異なります。
見た目、メンテナンス性、予算、用途の4つの観点から総合的に判断することで、芝生の代わりとして最適な素材を見つけることができるでしょう。
芝生をやめるという決断は、庭をより快適で機能的な空間へと進化させる第一歩となります。
ポイント
- 人工芝は見た目が自然で手入れがほぼ不要
- 砂利は手間がかからず和洋どちらにも合う
- タイルやレンガは実用性とデザイン性を両立できる
- グランドカバー植物は緑とナチュラル感が魅力
庭の芝生をやめる 費用と施工の目安
芝生を撤去し、別の素材に切り替える場合には、どれくらいの費用がかかるのか事前に把握しておくことが大切です。
施工の内容や規模、選ぶ素材によって金額は大きく変わりますが、おおよその相場を知ることで、無理のない計画を立てやすくなります。
まず、芝生の撤去だけでも費用が発生します。
業者に依頼する場合、1平方メートルあたり1,000円~2,000円が目安です。
これは、芝を剥がし、根や土壌表面を処理する作業にかかる手間と処分費用が含まれています。
自分で剥がすDIY方式であればコストを抑えられますが、肉体的な負担が大きく、庭の広さによっては数日がかりになることもあります。
撤去後に新たな素材を敷設する場合、その費用は素材ごとに異なります。
例えば、人工芝の施工は材料費込みで1平方メートルあたり4,000円〜8,000円程度、砂利敷きは2,000円〜4,000円程度が一般的です。
タイルやレンガを敷く場合には、下地処理も含めて1平方メートルあたり1万円を超えることもあります。
デザイン性や耐久性を求める場合は、その分費用が高くなる傾向があります。
加えて、施工方法によっても価格差が生じます。全面を業者に依頼するのか、一部をDIYで対応するのかによって、全体のコストは大きく異なります。
また、防草シートの設置や排水対策など、必要に応じた追加工事が発生することもあります。
施工を検討する際は、素材選びだけでなく、撤去・整地・敷設までの工程すべてを視野に入れた予算設計をすることが重要です。
見積もりを複数の業者から取ることで、費用の妥当性を比較しやすくなり、納得のいくリフォームにつながります。
ポイント
- 芝生の撤去だけで1㎡あたり1,000〜2,000円が目安
- 人工芝やタイルは素材によりコストが変動
- DIYと業者依頼では価格差が大きくなる
- 総額を見積もるには工程ごとの費用を把握することが大切
芝生をやめたあとに必要な土壌改良とは
芝生を取り除いたあとの庭では、次にどのような素材や植物を導入するかによって、適切な土壌改良が必要になります。
芝の根や古い土壌には有機物が残っていたり、水はけが悪くなっていたりするため、放置してそのまま次の施工に移るとトラブルの原因になりかねません。
まず最初に行うべきは、芝の根や茎を完全に取り除く作業です。
見た目には撤去できているようでも、地下に根が残っていると、時間が経ってから再び芽を出すことがあります。
特に野芝や高麗芝のような日本芝は繁殖力が強いため、表土を数センチ掘り返してふるいにかけるなど、丁寧な処理が求められます。
その後の整地では、必要に応じて「客土(きゃくど)」と呼ばれる新しい土を入れて地盤を整えます。
これは、元の土壌が粘土質で排水性が悪かったり、栄養バランスが崩れていた場合に特に有効です。
砂を混ぜて水はけを改善したり、腐葉土や堆肥を加えて有機物を補うことで、次に植える植物が根を張りやすい環境を整えられます。
また、防草対策もこの段階で行うと効果的です。
グランドカバーやハーブを植える予定がない場所には、防草シートを敷いてから砂利やタイルを重ねることで、雑草の再発を防げます。
一方、植物を植える予定があるエリアでは、必要以上に肥沃すぎる土は雑草の発生を助長してしまう可能性もあるため、調整が必要です。
水はけの悪さが気になる場所では、暗渠排水(あんきょはいすい)と呼ばれる排水パイプの設置を検討するのも有効です。
これにより、雨天後のぬかるみや水たまりを防ぎ、土壌環境を長く安定させることができます。
このように、芝生を取り除いたあとの土壌改良は、次の素材や植栽を成功させるための基礎工事といえます。
表面的な処理だけで済ませず、根本的な土壌の状態を見直すことが、快適な庭づくりの第一歩となるでしょう。
ポイント
- 芝の根の撤去が不十分だと再生する恐れがある
- 客土や有機質を加え、水はけや栄養を調整する必要あり
- 防草シートや排水設備の整備も効果的
- 次に植える素材に応じた土壌状態を整えることが成功の鍵
-

-
庭タープのおすすめ13選!支柱や張り方も紹介|庭ASOBI
本記事はプロモーションが含まれています 庭に張るタープのおすすめ13選と支柱・張り方・重り活用まで【完全解説】 庭に張るおすすめのタープを探している方にとって、どのタイプを選べばよいか迷うのは当然のこ ...
続きを見る
【まとめ】庭を芝生以外でおしゃれに仕上げる

芝生に代わる庭の選択肢は、見た目だけでなく、管理のしやすさや機能性など、多様なニーズに応えるものが数多く存在します。
以下に、この記事で紹介した主なポイントを整理します。
この記事のまとめ
- グランドカバー植物は雑草対策と景観維持に優れる
- 日照条件に合った植物選びが成功のカギ
- クラピアは繁殖力が高くメンテナンスが楽
- クラピアは苗販売のため初期費用がやや高め
- セダムは乾燥に強く、水やりの手間が少ない
- セダムは色や形が豊富でデザイン性も高い
- ハーブ系グランドカバーは香りと実用性を兼ねる
- タイル敷きは掃除が簡単でアウトドア利用に適している
- レンガはDIYでも取り入れやすく温かみのある印象を与える
- 砂利は雑草抑制や排水性の良さで管理がしやすい
- 人工芝は手入れ不要で一年中緑を保てる
- 素材によって初期費用と管理コストに大きな差がある
- 芝を剥がしたあとの土壌改良が成功の土台になる
- 用途とデザインに応じて素材を使い分けると効果的
- 防草対策や縁取り施工もあらかじめ計画しておくと安心
芝生だけにこだわらず、多様な素材や植物を組み合わせることで、庭はもっと自由で心地よい空間になります。
自分のライフスタイルや好みに合った快適なガーデンライフを楽しんでみてください。
庭を芝生以外にしたい!プロがすすめる代替素材ベスト5
- クラピア
- セダム
- ハーブ
- 砂利
- タイル・レンガ
-
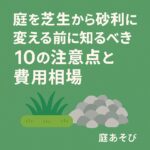
-
庭を芝生から砂利に変える前に知るべき10の注意点と費用相場|庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 庭を芝生から砂利に変えたいと考えている方の中には、 「手入れが大変」「芝生をやめるべきか迷っている」 このように感じている方も多いのではないでしょうか。 この記 ...
続きを見る
-

-
庭を芝生からタイルで快適!初心者向けの手順と注意点7つ | 庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 「庭の芝生をタイルに変えたい…」 上記のような悩みを抱える人の多くは、芝生の管理に疲れ、もっと手入れの少ない庭づくりを検討しているのではないでしょうか。見た目の ...
続きを見る
-

-
庭の芝生をやめたい人必見|手入れ不要に変える7つの方法|庭あそび
本記事はプロモーションが含まれています 芝生のある庭に憧れて張ってみたものの、 「手入れが大変」「放置するとすぐに荒れる」「管理の負担が大きい」 このように感じている方は少なくありません。 この記事に ...
続きを見る
庭を芝生以外にしたいと考える際にあるよくある質問(FAQ)
-
芝生をやめて別の素材にする場合、どれを選べば後悔しにくいですか?
-
まずは「庭をどう使いたいか」を基準に選ぶと後悔が少なくなります。
- 管理を最優先でラクにしたい → 砂利・人工芝
- 自然な緑を残したい → クラピア・セダム・ハーブ
- BBQやアウトドアリビングとして使いたい → タイル・レンガ
用途を明確にすると、素材の特徴(踏み圧に強い/弱い、初期費用、維持の手間)が比較しやすくなり、最適な選択ができます。
-
芝生を剥がしたあとの土壌、どこまで処理すればいいの?
-
最低限、「芝の根の完全撤去」と「水はけの確認」は必須です。
- 根が残る → 芝が再び生える
- 水はけが悪いまま → 砂利やタイルでもトラブル発生
植物を植える場合は客土や堆肥で改良し、砂利・タイルを敷く場合は防草シート+整地をセットで行うと失敗しにくいです。
-
クラピアとセダム、どっちが初心者向け?
-
「手入れの少なさ」を重視するならセダム。
「芝生のような広がる緑」を求めるならクラピア。- クラピア: 繁殖力◎、見た目◎、ただし初期費用がやや高い
- セダム: 乾燥に強い・ほぼ放置OK、踏み圧には弱い
子どもがよく歩く庭ならクラピア、乾燥が気になる庭ならセダムが向きます。
-
砂利にしたいけど、見た目が単調にならないか不安です。
-
砂利は色・サイズの組み合わせで印象を大きく変えられます。
さらに以下を組み合わせると一気に“庭っぽさ”が出ます。- 砂利+踏み石
- 砂利+グランドカバー植物
- 砂利+レンガの縁取り
単体で使うよりも、複数の素材を組み合わせることで、雑草対策を保ちながらデザイン性を高められます。
-
DIYでタイルやレンガを敷いてもいい?専門業者のほうが良い?
-
小規模ならDIY、大規模なら業者が安心です。
DIYに向くケース
- レンガを並べる“簡易施工”
- 小さなアプローチづくり
- 部分的な砂利+飛び石
業者に依頼すべきケース
- タイルの下地づくり(排水勾配が必要)
- 庭全体の舗装
- 水はけの悪さが気になる場合
タイル施工は下地のミス=割れ・沈み・水たまりに直結するため、プロの施工が安心です。
